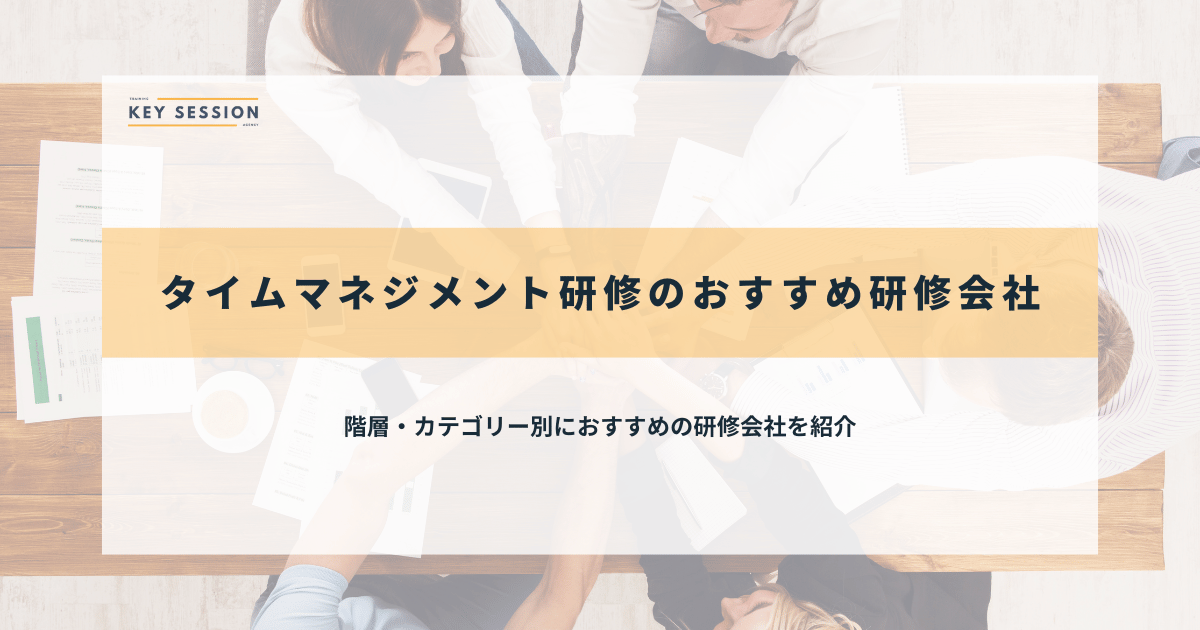企業の教育担当から挙がる課題や悩み
①【業務の進め方】の悩み(=時間の使い方が非効率)
- 業務量が多く、「何から手をつけるべきか」が曖昧なまま一日が終わってしまう
- ToDoリストは作るが、優先順位が曖昧で結局後回しになる
- 急ぎの対応に追われ、重要な仕事に集中できない
- ダブルブッキングや抜け漏れが多く、信頼性を欠いている
- スケジュールがパンパンで、考える時間・準備の時間が取れない
- 「効率的」なやり方が個人任せで、属人化している
②【生産性・残業削減】の悩み(=働き方改革が進まない)
- 働き方改革を進めたいが、現場は「忙しい」から抜け出せていない
- 残業時間は減らしたいが、削っても業務が終わらず結局持ち帰りに
- 時間の使い方に対する“意識差”がチーム内で大きい
- 生産性を高める具体的なアプローチが浸透していない
- 繁忙期のマネジメントが属人的で、毎回場当たり的になっている
③【人材育成・若手教育】の悩み(=段取り力・自律性の欠如)
- 若手が「段取り」や「時間の見積もり」が苦手で、行き当たりばったりになる
- 上司がいちいち指示しないと動けない=自律性が育たない
- 失敗しても“振り返る習慣”がなく、改善に繋がらない
- 仕事を任せても、時間配分やスケジュール設計ができないため、任せきれない
- 学習や自己成長の時間が後回しにされ、スキルアップが進まない
④【チームマネジメント】の悩み(=時間の使い方に対する温度差)
- メンバーの時間感覚にバラつきがあり、スケジュールがうまくかみ合わない
- チームとしての「計画→実行→振り返り」のサイクルが回っていない
- 管理職が多忙すぎて、育成や改善の時間が取れない
- 業務の属人化が進み、誰が何をしているかが見えにくい
⑤【組織文化・意識改革】の悩み(=時間の価値が軽視されがち)
- 「忙しいことが良いこと」という文化が根強く残っている
- 無駄な作業や非効率なやり方を放置している
- “成果で評価”ではなく“頑張っている姿勢”が重視されがち
- 時間の使い方についてのフィードバックや評価が曖昧
- 変化に消極的で、「改善する時間すらない」と諦めモードになっている
研修の目的
「忙しさに追われる人材を“時間を設計する人材”へ」
本研修の目的は、社員一人ひとりが“限られた時間をどう使うか”を戦略的に考え、単なる「作業者」ではなく、自らの時間を設計し成果を出す“自律型人材”へと進化することです。
- 日々の業務を「処理する対象」ではなく、「成果を生む投資対象」として捉える視点を養う
- タスクの可視化・優先順位付け・スケジューリングの技術を習得し、実行力と段取り力を高める
- 振り返りと改善を習慣化し、計画→実行→検証→再計画のサイクルを回せるようにする
- 仕事の「やるべきこと」と「やらないこと」を見極め、限られた時間で成果を最大化する力をつける
- 組織内でのスケジュール共有や時間の使い方に対する意識を揃え、チームの生産性を底上げする
- ワークや演習を通して、自身の業務を題材にしたタイムマネジメントを体感し、即実践に移せる状態をつくる
研修の特徴 〜時間の使い方を「武器」に変える〜
1. タイムマネジメントを「成果創出の戦略」として再定義
時間管理を“単なる効率化”ではなく、「成果を出すための戦略」として捉え直します。
働き方改革や残業削減といったテーマにも直結する、本質的な時間の使い方を学びます。
2. 実務直結型のスキルを“体系的・段階的”に習得
タスク整理、優先順位づけ、スケジューリング、振り返りといったスキルを、ワーク+解説+実践計画の流れで、段階的に自分の業務に落とし込んでいきます。
「計画して終わり」ではなく、明日からの行動が変わる実践力を身につけます。
3. 「学園祭」モチーフの体感型ワークで本質を楽しく学ぶ
「楽しく、でも本気で考える」学園祭エクササイズで、タスクの優先順位づけや計画立案を体験。
個人とチームの時間の使い方を同時に学べるワークで、納得感と行動変容が高まります。
4. 業務の棚卸しからスケジュール化まで、自分の仕事で実施
単なるロールプレイではなく、自分の業務をその場で振り返り・設計するスタイル。
先週のタスクを棚卸し、来週のスケジュールに落とし込むことで、研修中に行動計画が完成します。
5. 受講後も実行できる「習慣化」設計
振り返りフォーマットや行動目標の設定など、実践を支える仕組みも提供。
希望に応じて、研修後のレビューシート提出やフォローアップ面談の設計も可能です。
「学んで終わり」にせず、行動定着と自走力向上を支援します。
研修の効果(受講後に期待できる変化)
意識・視点の変化(マインドセット)
- 時間=リソースという経営視点が育つ
単なる「忙しさの管理」ではなく、「成果を最大化する時間の使い方」への意識変化が生まれる。
限られた時間で何を選ぶか、意思決定の質を高める視点を得る。 - 「やることを増やす」から「やらないことを決める」へ
全てを完了させる発想から、重要なことに集中するマインドへの転換。
「削る勇気」「任せる戦略」をもつ。
- 「計画=自由を生む」という捉え方が身につく
スケジュールやToDoリストは縛りではなく、自由と成果のためのツールであると理解する。
スキル・行動の変化
- タスク整理・優先順位付けの技術が身につく
タスクの棚卸し → 工数の可視化 → 重要度・緊急度での整理 → 時間ブロックでの落とし込みまでを自力で実行できるようになる。 - 振り返りと改善が習慣化する
「できた・できなかった」だけでなく、「なぜそうなったか」「次にどう改善するか」を考える週間レビューの力が身につく。 - 計画から実行への橋渡し力が高まる
立てたスケジュールを現実的に実行するための段取り力・見積もり力が向上する。 - 業務効率よりも成果効率を意識できる
作業量をこなすのではなく、最小の時間で最大の成果を出す思考・行動が身につく。
組織への波及効果
- チーム内での時間感覚・スケジュール感が揃う
計画を共有する文化が生まれ、業務のズレ・ムリ・モレが減る。 - “忙しい”が口癖の職場から、“成果を出す”が共通言語の職場へ
時間を「奪い合う」状態から、「価値ある使い方」を話せる組織風土に変わる。 - 業務の属人化やタスクのブラックボックス化を防げる
タスクやスケジュールの見える化が進み、誰が・いつ・何をしているかが共有されやすくなる。 - メンバーが「指示待ち」から「自律型」へ変化
自身でスケジュールを立て、主体的に動ける人材が増え、マネジメントコストが軽減される。