
ビジネスにおいて問題解決の重要性は頻繁に語られますが、問題提起の重要性についてはあまり話題に上りません。問題提起は企業の問題解決の出発点となるものです。
この記事では、ビジネスにおける問題提起の定義・必要とされる理由・手順・注意点などを解説します。
問題提起から解決までのスキルを高めるなら、問題解決研修の実施がおすすめです。体系立てて問題解決のスキルを学べるうえ、研修によってはケーススタディで実践力も高められるからです。
キーセッションでは予算と目的を共有いただければ、貴社にぴったりな問題解決研修をご提案できます。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
実践的な問題解決スキルを身につけるための研修。プロの指導のもと、実際のビジネスシーンでの課題を解決する手法を学びます。研修を通じて、即戦力としての能力を高めることができます。
問題提起とは?
実用日本語表現辞典によると、一般的に「問題提起」とは「問題や課題を解決すべき事項として投げ掛けること」を意味します。
この章では、ビジネスにおける問題提起の意味や目的を解説します。
ビジネスにおける「問題提起」の意味
ビジネスにおいて、問題提起の基本的な意味は変わりません。すなわち、課題や解決すべき事案を問題として取り上げるように提唱することを意味します。
より具体的にかみ砕いて説明すると、問題とはビジネスにおける理想の状態と現状とのギャップのことです。つまり問題を解決することは企業を理想の状態へと近づけることを意味します。したがって、問題提起から解決の過程はビジネスそのものであるといっても過言ではありません。
なぜ問題提起をする必要があるのか
問題提起をしない状況については、2つの段階が考えられます。
1つ目は、問題の存在に気付いているにもかかわらず、リーダーや社員が問題提起しない状態です。いわゆる「事なかれ主義」の状態です。
チームの責任者やメンバー全員が「事なかれ主義」の状態であると言うことは、理想の状態とのギャップがあることを分かっているにもかかわらず、その改善を放置していることを意味します。いわば、非常に無責任で他人任せの状態であるといえます。
2つ目は、そもそも問題の存在を認識していない状態です。問題は、発見が遅くなればなるほど問題は大きくなります。
両者に共通する問題としては、問題を提起しないあるいはできないことにより、課題がそのままの状態で残され大きなトラブルに発展しかねません。
問題提起の類義語や言い換え
問題提起にピッタリとマッチする類義語はありませんが、「提起」の部分の類義語をチェックすることで、問題提起の用語のイメージを深められます。
これらは、いずれも会議などで案を出すことを意味します。
つまり、問題定義は会議などに問題として提案をすることを意味します。
また、ビジネス用語は海外から入ってくることが多いため、英語に置き換えることで、用語のイメージがよりハッキリすることもあります。参考までに、英語で「問題提起」を表現するフレーズを紹介します。
・problem presentation:直訳すると、問題+提案・説明といった意味合いです。
・raising of questions:”raising”は、上昇を意味する単語ですが、考慮や議論のために提案するという意味もあります。
英語で考えるとよりビジネス要素の強い用語であることが確認できます。
問題提起の手順

リーダーや社員から問題提起がされ、改善が繰り返されている組織は、組織として理想的な状態です。そうあるためには、理想的な問題提起の手順を設定する必要があります。
この章では、問題提起の3つのステップ(手順)を解説します。
ステップ1:理想のイメージを書き出す
問題提起のために最初におこなうべきことは理想のイメージの状態を洗い出すことです。個人売上などが好調な場合は、数ヶ月後・1年後と好調を維持・発展できているか否かをイメージすることが大切です。このとき、数値化できる定量的な観点と数値化の難しい定性的な観点との両方の視点で、できるだけ多くの項目でイメージを思い浮かべるようにしましょう。
チームとしてイメージの洗い出しをする場合には、下記の方法があります。
・従業員アンケーットで書き出してもらう
・ブレインストーミング
・個別面談
組織として複数の社員に理想のイメージを確認した場合には、ツールやExcelなどによりデータベース化することで、理想が可視化されます。
ステップ2:現状を把握する
続いて、現状のビジネスがどのようになっているのかを確認します。現状把握についても定量的・定性的データをそれぞれピックアップします。
【定量的】
・売上の推移
・コスト
・残業時間
【定性的】
・チームの風通しの良さ
・業務のやりがい
・仕事の満足度
特に定性的な面の現状把握については、複数のスタッフに意見を聞いて多角的に判断することが重要です。
ステップ3:理想と現実のギャップを確認する
理想と現状が確認できたら、両者を項目ごとに比較をして、理想と現実のギャップについてまとめます。
そして、このギャップを問題として提起すべきか否かを検証します。
具体例をいくつか見てみましょう。
【ケース1】
(理想)社員の育休取得率70%
(現実)社員の育休取得率40%
(問題提起)社員の育休取得率のアップ
【ケース2】
(理想)全部署での情報共有がスムーズである
(現実)営業部とマーケティング部とでうまく連携が取れていない
(問題提起)営業部とマーケティング部の情報共有を改善すべき
問題提起すべき事案が決まったら、会議での議題にしたり個別ミーティングにしたり、リーダーが積極的に関与したりして問題解決を目指します。
問題発見能力を高める方法
問題提起のために最もネックになる部分は、問題発見力です。そもそも発見できなければ問題は最初から存在しないことになります。
この章では、問題発見力を高めるための考え方やポイントを解説します。
クリティカルシンキングを身につける
問題提起のためのベースとなるのは、クリティカルシンキング(批判的思考)です。
クリティカルシンキングとは、物事を批判に捉える考え方のことです。従来では常識と考えられている慣習や仕事の進め方を含めあらゆることに批判的な見方をすることで、柔軟に本質を見抜くことが可能になります。
クリティカルシンキングの考え方を身につけるためには、客観的な視点で事実に基づいて物事をとらえるクセをつけることが大切です。エッセンスを学ぶためには、外部研修会社にてクリティカルシンキング研修を学ぶことが最も効率的です。
クリティカルシンキングとは、「批判的思考」と解説されます。砕いて説明をすれば、「本当にそうなの?」と疑う視点を持つ思考です。クリティカルシンキング研修ではより「本質的」な事を考える事につながる思考の基本とビジネスでの活用方法を学びます。
社内コミュニケーションを高める
課題発見は、社員1人がおこなうよりもチームで取り組んだ方がスムーズにいきます。チームで課題を発見する際に重要な役割を果たすのが、コミュニケーションです。
特に、相手方の意見を引き出したり、態度や所作から情報を感じ取ったりする傾聴の能力をたかめることで、チーム内での疑問・不満などが吸い上げられるうになります。
フレームワーク・会議手法を活用する
問題を発見して議題としてまとめるためには、以下のフレームワークや会議手法が活用できます。
・ブレインストーミング
・グルーピング・・・個々の意見を、関連性のあるグループにまとめて、整理することです。
・ロジックツリー・・・上位の問題(根本の問題)と下位の問題(根本的な問題から生まれた個別の問題)に分けることで、根本の問題を発見できます。
仮説思考を身につける
問題発見のためには、起こっている事象から課題が何なのかを仮説として考えることが重要です。例えば、特定の商品に対してクレームが頻発している場合に、
- 商品の品質が悪い
- 人員不足のためサービスが低下している
- 価格設定が高すぎる
など、何を問題とすべきかの仮説を立て、検証した上で問題提起をおこないます。
問題提起のポイントや注意点

問題提起により、チームをより良い状態に近づけるために押さえておきたいポイントと注意点を解説します。ポイントを押さえることで、より効果的・効率的にチームを問題解決へと導くことができます。
問題の根本の原因を考える
ビジネスにおいて生じている問題には、根本の原因となっている問題と派生的な現象としての問題があります。このとき、根本的な問題解決に取り組まなければ、チームとして理想の状態に近づくことは不可能です。また、根本の原因を理解することにより、問題解決の道筋が明確になり問題に取り組みやすくなります。
従って、問題発見の際には常に何が原因となっているのかを考え、検証するようにしましょう。
問題の数を絞る
ブレインストーミングなどで問題を数多くピックアップすることは大切ですが、問題が増えすぎると取り組むべき問題が見えづらくなります。
関連性のあるもの・内容が似ているもの・同じ原因から発生しているものなどをグループ化して一つの問題として取り組むことにより、チームが取り組むべき問題を絞ることができます。問題を切り捨てるという意味ではなく、取り組みやすくまとめることが重要です。
5W1Hを考える
問題をロジカルに考えて分かりやすくするためのポイントとして、5W1Hを意識することも重要です。
問題に関して、「誰が」「いつ」「何を」「どこで」「なぜ」「どのように」起こっているのかを考えることで、問題を分かりやすくメンバーに伝え、共有することができます。
問題を考え続ける
問題提起・問題解決によりチームの改善を図るときには、一度だけミーティングなどで問題提起の場を設ければよいということではなく、問題を考え続ける姿勢も重要です。日常的にチームの全員が問題発見・提起の意識を持ち続けることにより、常に改善を意識した優れた組織に成長できます。
問題提起されたときに気をつけること
社員からの問題提起を問題解決に生かすためには、受けた側が注意すべきポイントがあります。
この章では、問題提起をされたときに経営者やリーダーが注意すべきポイントを解説します。
否定をしない
スタッフが問題提起をしたにもかかわらず否定から入ってしまうと、問題提起をしづらい雰囲気になります。「提案をしても受け入れられない」との思いから、チームの状態としても望ましくない状態に陥るといえます。
ポイントは、リーダー自身はもちろんのこと組織全体で問題提起を歓迎する姿勢を作ることです。理由や詳細を確認する際に「なぜ~できないのか?」ではなく「どのようにすれば~できるのか?」を意識して問題を整理することで、問題提起しやすい雰囲気が生まれます。
解決策を求めない
問題提起をしたスタッフに対して解決策を求めてしまいがちですが、問題提起と問題解決は分けて考えましょう。なぜなら、問題の発見自体が非常に貴重なことだからです。
解決策を求められると、スタッフ側にとっては問題提起のハードルが高くなります。結果的に報告のタイミングが遅くなったり、結局報告されないまま終わってしまったりすることになるのです。
他のスタッフが優れた解決策を示すことや、会議などで全員で答えを模索することによって、チームがより良い方向に向かいます。
ゼロベース思考をもつ
ゼロベース思考とは、簡単にいえば思い込みや規定概念をゼロにする考え方のことです。クリティカルシンキングにもつながることですが、思い込みや規定概念に左右されると、問題提起をされても否定をしてしまいがちです。そもそも、ゼロベース思考をもてていないと、なかなか問題提起が上がってこないのです。
問題提起能力を養うには、問題発見や問題解決の方法論を実践できるようになる学びを取り入れるのが有効です。組織を活性化させるために、研修を取り入れていきましょう。
問題解決のレシピ【デザイン思考研修】 (8時間)
チームで“真の問題”を発見し、ユーザーを感動させるアイデアを創出するデザイン思考を体感型で学べる実践的な研修です。




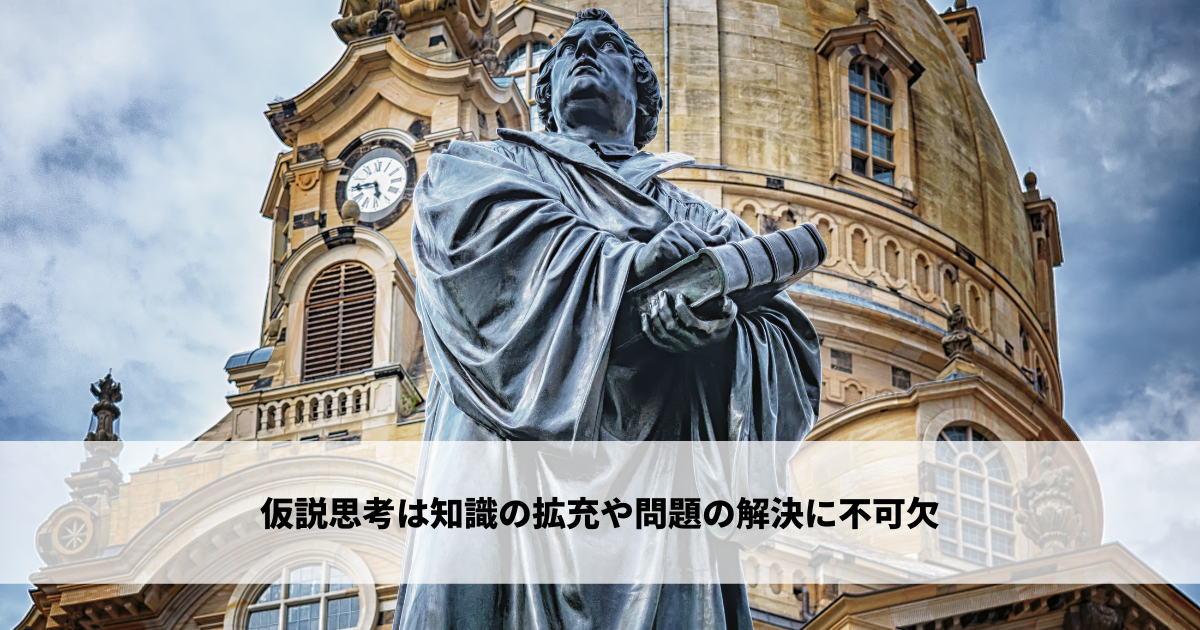




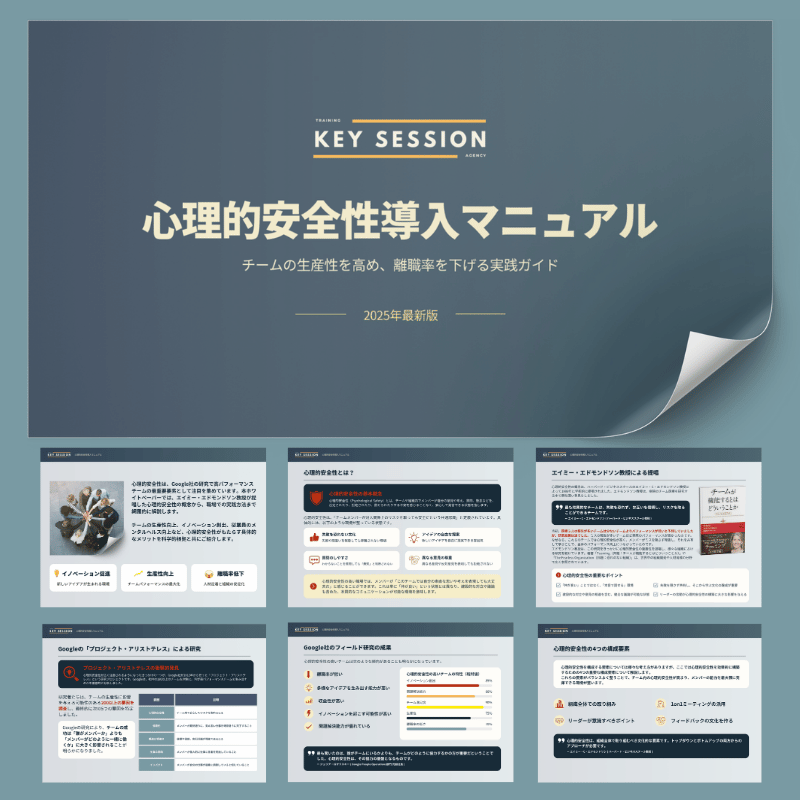


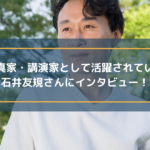
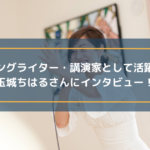
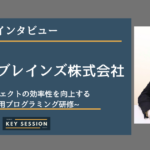



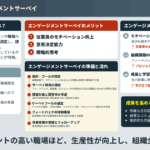



 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート