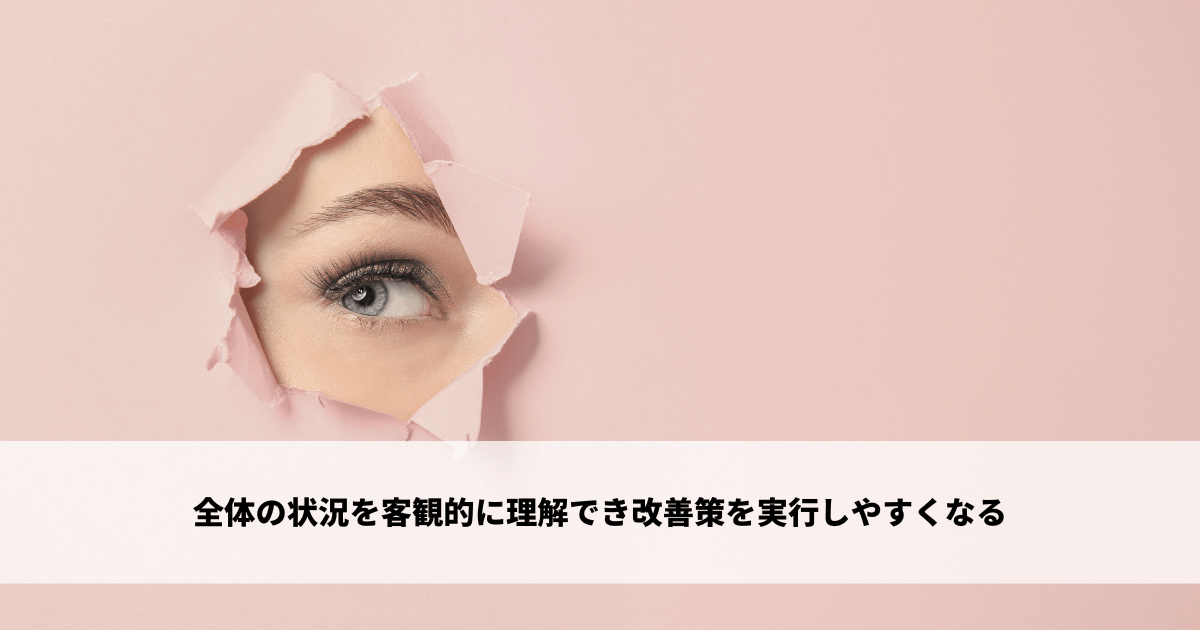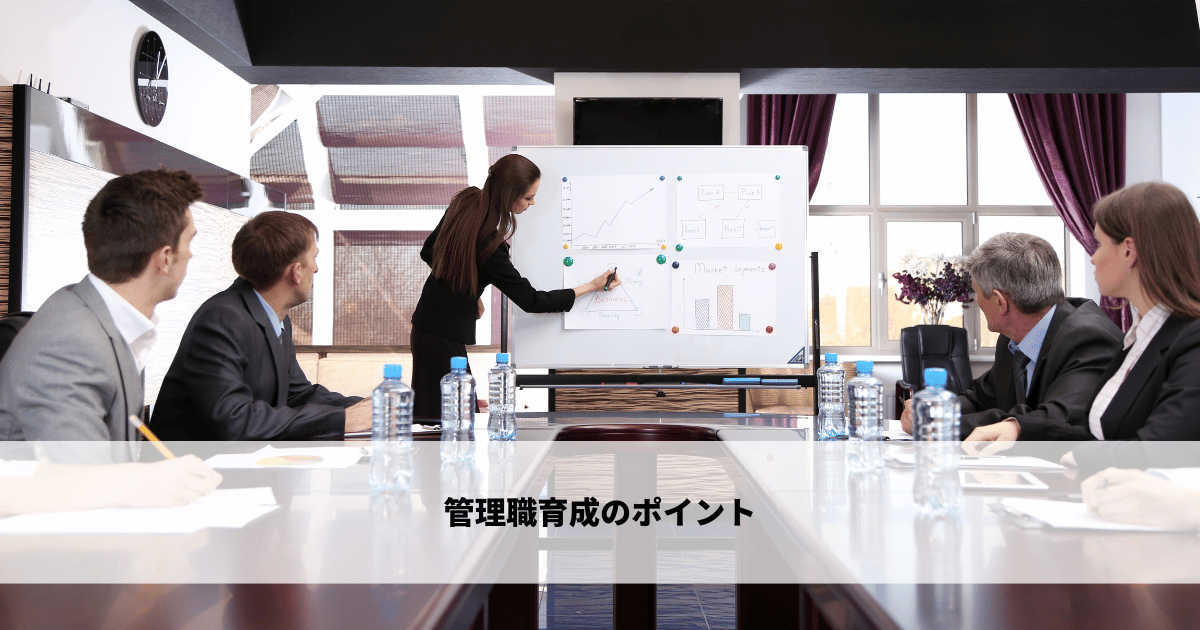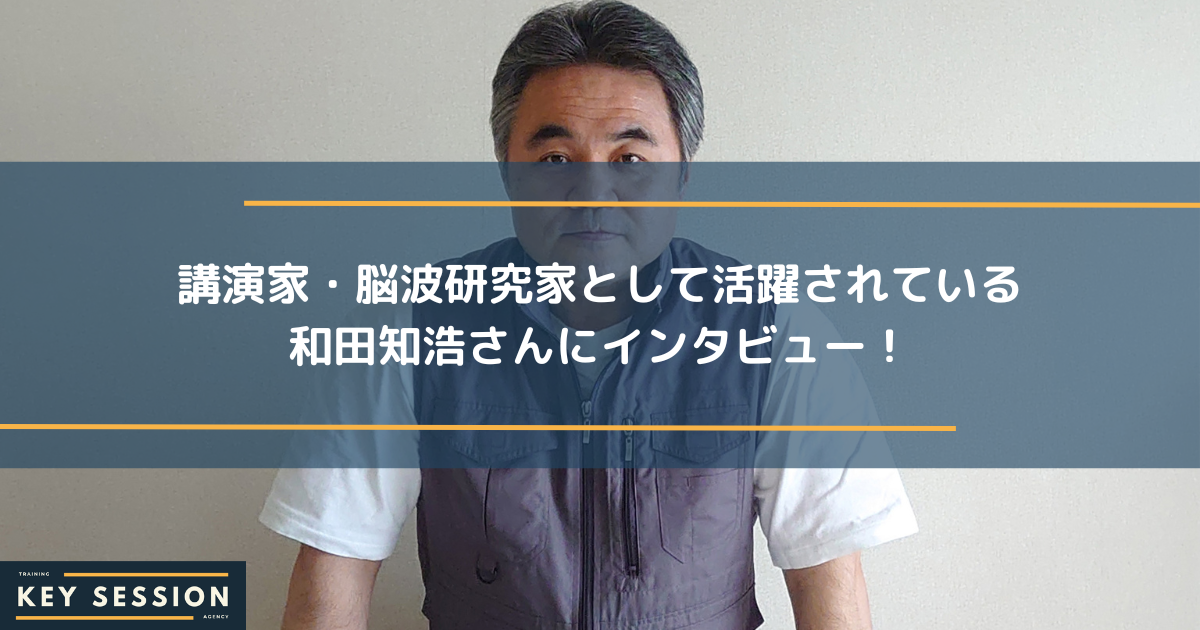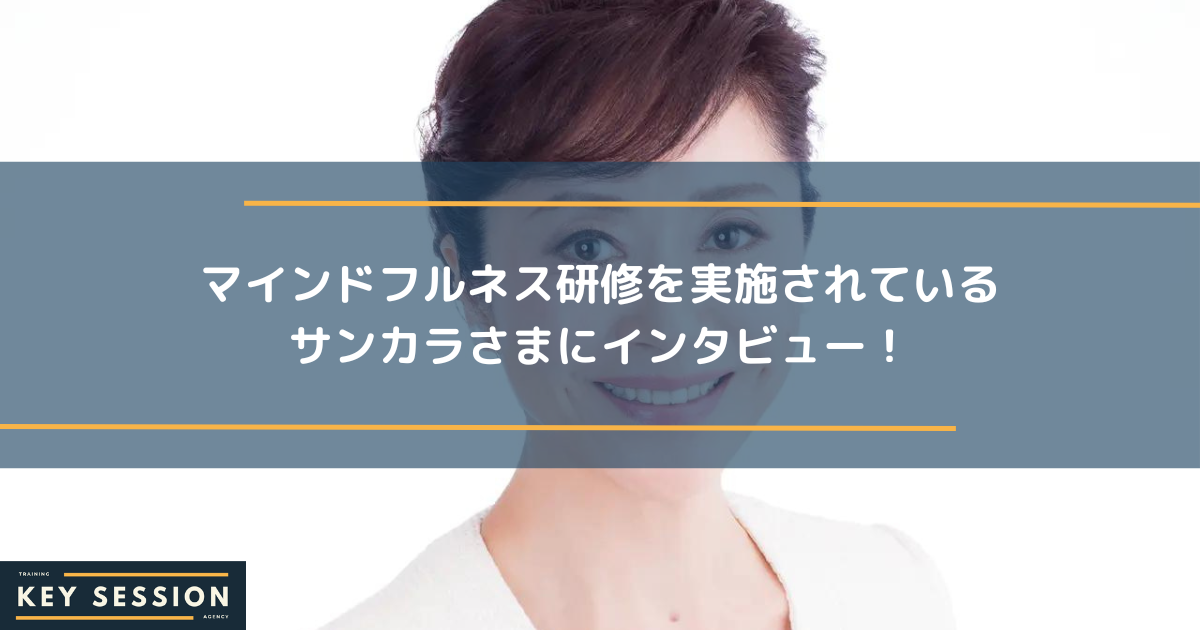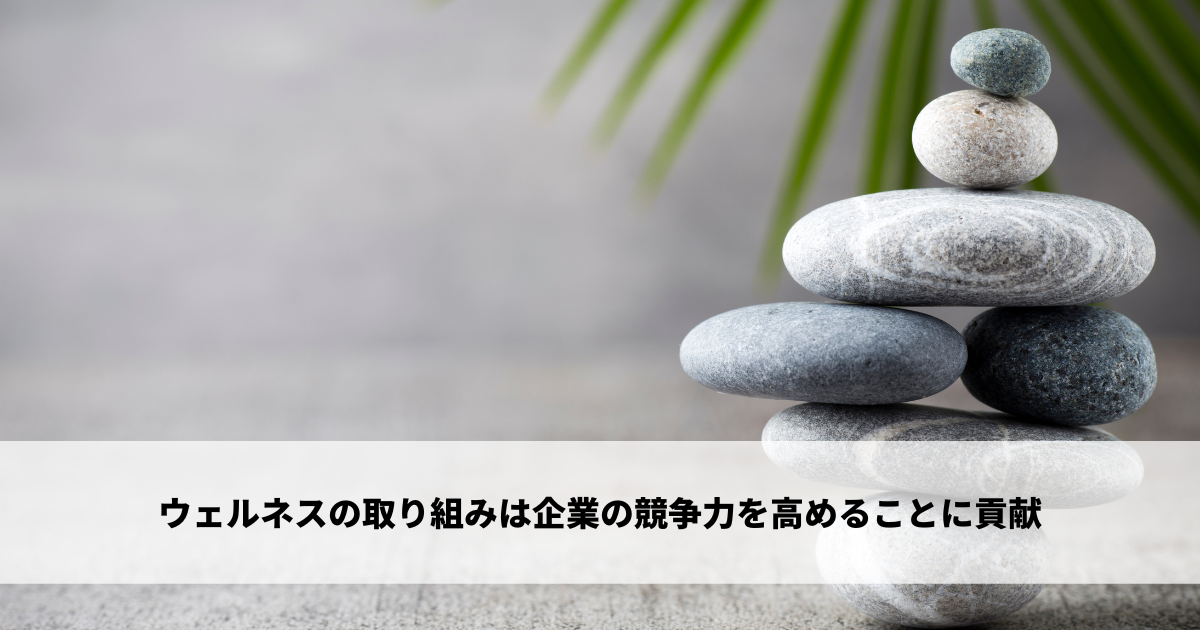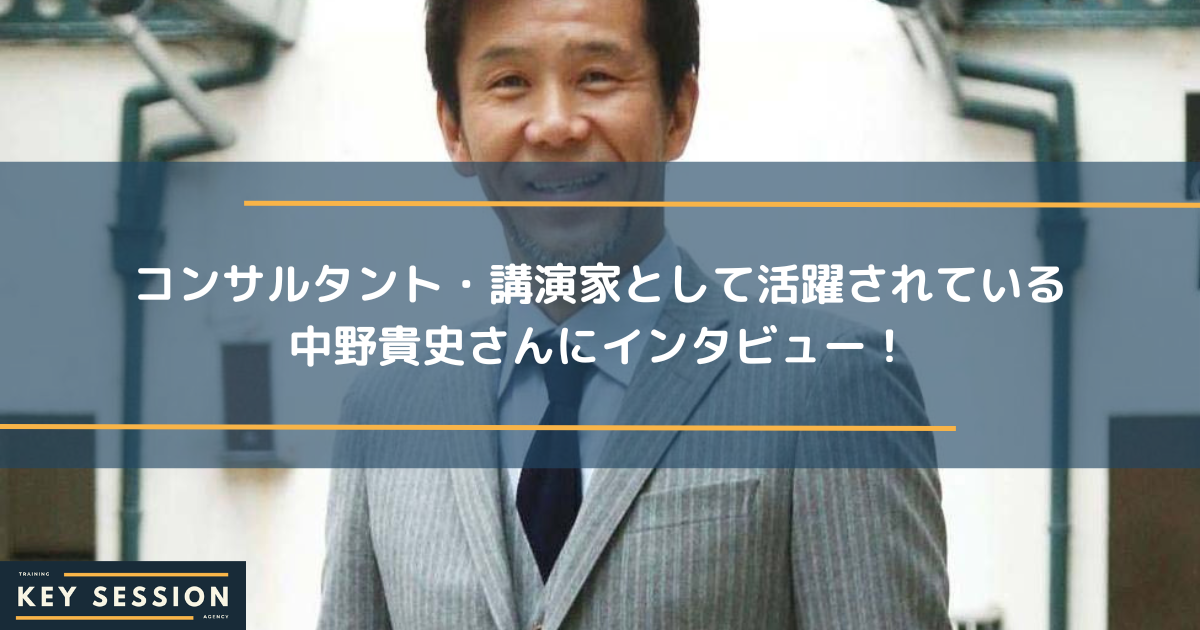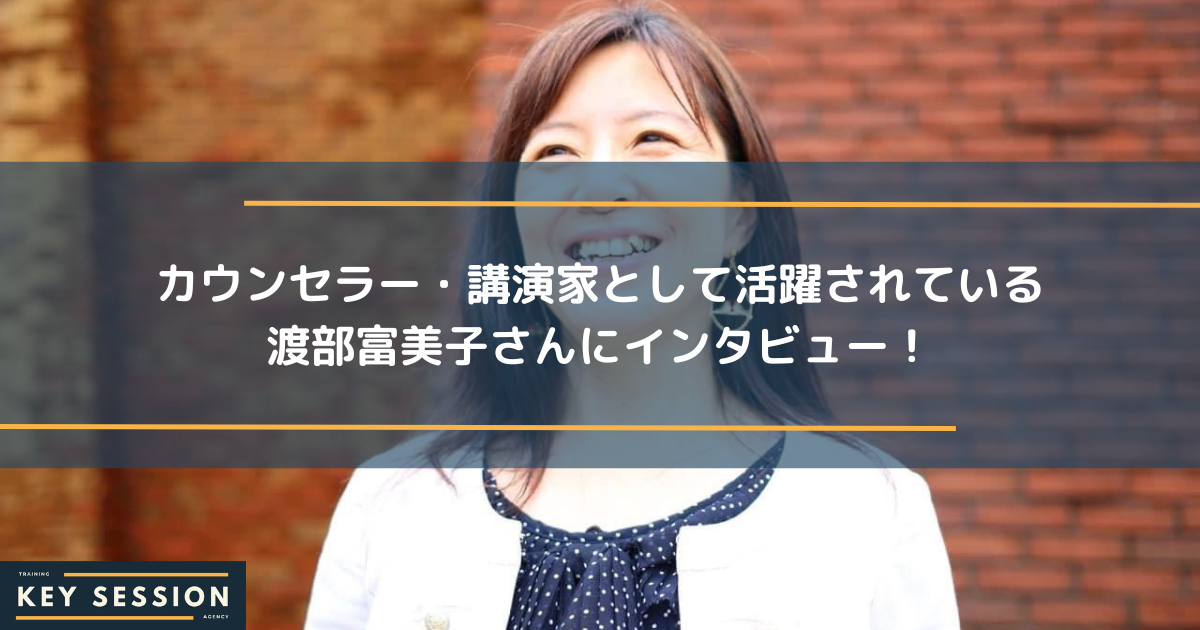「メンタルヘルス研修では、どのでような内容を学べるかわからない」「メンタルヘルス研修を実施することで、どのような効果があるの?」
このような疑問や悩みを抱えている経営者や責任者も多いのではないでしょうか。
当記事では、メンタルヘルス研修の目的やカリキュラム例、おすすめのメンタルヘルス研修について紹介していきます。メンタルヘルス研修を検討している担当者の方は、ご一読ください。
この記事でわかること
- メンタルヘルス研修の目的
- メンタルヘルス研修のカリキュラム例
- おすすめのメンタルヘルス研修
メンタルヘルス研修を実施する際は、研修の内容や講師の質が重要です。しかし、数多くの研修会社から適した研修を選ぶのは困難ではないでしょうか。キーセッションでは、複数の研修会社の中から貴社のご要望に沿った研修会社のご案内が可能です。相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

メンタルヘルス研修とは?内容を解説
メンタルヘルス研修とは、心の健康を維持し、管理するためのスキルや知識を学ぶ研修です。メンタルヘルスは日本語で「心の健康」を意味します。
精神的な病を表す用語と誤解する方がいますが、本来は会社や家庭、社会で活力を持ち生活できる精神状態を「メンタルヘルス」と呼びます。
研修で学ぶ内容は、以下の2つです。
- 社員の精神的な病を日頃から予防するための知識
- 心の病が発生した場合に適切に対応する方法
メンタルヘルス研修では、社員が心の健康を維持し職場でイキイキと働くために、この2つの側面からメンタルヘルス対策について学習します。
心の病になる要因は、人間関係や仕事の内容、ハラスメントなど人により異なります。研修で学習した内容を活用して、職場の環境や部下とのコミュニケーションを見なおし、ストレスを減らし働らける環境を整備していきましょう。
- ポジティブなメンタルヘルスにより、人々は次のことができます。
- 潜在能力を最大限に引き出す・人生のストレスに対処する・生産的に働く・コミュニティに有意義な貢献をする
《出典》 メンタルヘルスとは? - MentalHealth.gov
メンタルヘルスが重要視されている理由
メンタルヘルス研修が重要視されている理由はさまざまです。
たとえば、自殺者の増加はメンタルヘルス研修が必要と言われる理由の一つです。厚生労働省の調べでは、10代〜30代における死亡原因の第3位以内に自殺がランクインしています。
参考:死因順位別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合
また、現代ではうつ病を公表する人も増えており、身近な社員がうつ病の場合や、新入社員がうつ病経験者の可能性も考えられます。
そして、2015年12月より50名以上の従業員が在籍する会社に「ストレスチェック制度」の導入が義務付けられたことも、メンタルヘルス研修の需要が高くなっている要因といえます。「ストレスチェック制度」は、従業員のストレスを把握し、心の健康や会社の労働環境を改善をするために、国が推し進めている制度です。
自殺者やうつ病者の増加に加え、国が会社の労働環境の改善を進めていることが、メンタルヘルス研修が必要といわれる理由です。
メンタルヘルス研修の目的・効果
メンタルヘルス研修には、以下の3つの効果や目的があります。
- 働きやすい職場づくり
- 社員の生産性やモチベーションの向上
- 社員の離職防止
働きやすい職場づくり
誰もがストレスが少なく働ける職場づくりは、メンタルヘルス研修の主な目的です。
研修を受けると、「ストレスは人により受け取り方が異なる」ことを社員が学びます。ストレスの受け取り方の違いを社員が共通認識としてもつことで、お互いに配慮したコミュニケーションが生まれ、ストレスの少ない職場環境につながるのです。
そして研修を受けることで、ストレスを溜め込んでいる場合でも、周りに相談しやすい環境が整えられます。
研修によって働きやすい職場環境にするためには、メンタルヘルスに深い知見のある講師を呼び、会社にどう落とし込むかまでを考慮した内容を計画するのが大切です。
社員の生産性やモチベーションの向上
メンタルヘルス研修は、社員の生産性やモチベーションの向上に効果的です。
研修では、ストレスを受けたときの状態を複数のタイプに分けて、一人ひとりに合わせた対処法を学びます。社員が自身のストレスを理解して、ストレスを発散する術を身につけることで、心の病が悪化する前に対応できます。
ストレスを溜め込みながら仕事をする人と、うまく発散できる人とではモチベーションに差があるのは明らかです。研修では社員がメンタルケアをより自身のことと受け止めてもらうために、実践的な研修内容を多く取り入れましょう。
社員のモチベーションや生産性を向上させるためには、日ごろからメンタルヘルスの情報を発信することが大切です。
社員の離職防止
メンタルヘルス研修には、社員の離職防止の目的があります。研修では、社員自身のストレスと向き合う「セルフケア」と、管理職が部下のストレス状態を把握する「ラインケア」の2つを学びます。
社員自身のストレスと管理職の部下へのストレスケアの2つの視点からメンタルヘルスを学ぶことで、離職を防ぐ効果が期待できるのです。
精神疾患などによる社員の休職は、現場に負担をかけたり、メンタルヘルス不調の連鎖を招いたりする可能性があります。その結果、社員が離職すると会社の業績にも影響しかねません。
研修で「セルフケア」と「ラインケア」について深く学び、社員が自身でメンタルケアを行い、活力を失わずに働き続けられる職場を目指しましょう。

メンタルヘルス研修のカリキュラム例
メンタルヘルス研修のカリキュラム例は、以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | チームや組織のメンタル問題への対処を求められる、中堅~管理職の社員 |
| 目指すゴール | 1.メンタルヘルスの基礎知識の習得(セルフケア・ラインケア) 2.後輩・部下の業務管理とコミュニケーション手法を学ぶ 3.実際の現場でメンタルヘルスケアを実践するきっかけを得る |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入 | ◆現代社会のメンタルヘルス問題 ◆ワーク:自分の物事の捉え方について傾向を知る ⇒認知行動療法にもとづく5つの傾向 1)0か100かで判断する 2)議論を一般化する 3)マイナス思考 4)すべき思考 5)レッテル貼り |
| メンタルヘルスケアの基礎知識 | ◆セルフケア編 ・職場に存在するさまざまなストレス要因 ・ストレスと適切に向き合うには ◆ラインケア編 ・メンタルヘルスケアに関する法令・制度を知る ・メンタル不調の兆候をとらえるには |
| メンタル不調を防ぐ職場づくり | ◆後輩・部下の業務管理 ・進捗管理と問題点の指摘方法 ・業務過多になっていないかチェックする ◆ハラスメントの予防と対処 ・自身が加害者とならないために重要な考え方 ・ハラスメントの報告を受けたときの対処法 |
| まとめ | ◆誰もが安心して働ける職場にするために ・後輩や部下の承認欲求を満たす言葉がけをしよう ・ポジティブな言葉づかいをしよう |
【対象者別】メンタルヘルス研修で学ぶべき内容
メンタルヘルス研修で学ぶべき内容は、研修の対象者によって異なります。ここでは、以下の3つの対象者別に、研修で学ぶべき内容を紹介していきます。
- 一般社員
- 管理職
- 介護・医療従事者
一般社員は基礎的な内容
一般社員が学ぶのは、メンタルヘルスの基本的な内容です。主に、以下の4つの内容を中心に学習します。
- ストレスそのものについて基礎知識
- ストレス状態から抜け出すための対処法
- 会社の職員と円滑に付き合うためのコミュニケーション方法
- メンタルの調子がよくないときのサインに気づくための知識
現場で働く一般社員は、顧客や取引先と関わる場が多く、ストレスを受けやすいです。忙しさから余裕がなくなり、自身のケアが後回しになることで、心の病が深刻な状況になってからメンタルヘルス不調を自覚するケースも少なくありません。
そのため、一般社員はまずはストレス自体の理解と自身のストレスのケア方法や、職場での円滑なコミュニケーション方法など基本的な内容から学ぶことが効果的です。
管理職は部下のメンタルヘルス管理
管理職は、部下のメンタルヘルス管理について研修で重点的に学びます。中心的に学ぶのは、以下の内容です。
- 部下のメンタルの悪化やストレス状態に気付く方法
- チームメンバーがストレスなく働ける環境づくり
- 部下と円滑なコミュニケーションをとるための方法
チームの指揮を任されている管理職は、仕事の進行度合い以外にも、部下のメンタルケアにも配慮して、業務が滞りなく進むようフォローする能力が要求されます。しかし、中には進行具合にばかり気を取られ、部下のメンタルケアに手が回らない会社が多いのが現実です。
メンタルヘルス研修から、部下のメンタル管理方法を学ぶことで、相談しやすい雰囲気が生まれ、メンタル面の異変にいち早く気づける環境づくりにつながります。
介護・医療従事者は現場の課題に沿った内容
介護・医療業界は、人の命に関わる仕事であることから、責任が重くストレスを受けやすい職業です。とくに現場の職員の責任が重いため、メンタルヘルス研修では、現場に合わせた内容が求められます。
介護・医療従事者は「現場の社員」と「管理職」で、それぞれ以下の内容を学びます。
【現場職員の研修内容】
- 自身の頭の考え方のタイプを理解し、メンタルヘルスの悪化を予防する
- ストレスを受けた場合の思考法や対応方法
【管理職の研修内容】
- 部下に心の病やメンタルの不調に対しての相談を受けたときの対応方法
- 利用者、患者などによるハラスメントを援助するための仕組み構築
福祉、医療業界は、勤務の形態や仕事内容の特殊さ・過酷さが一般企業とは異なるため、職場の状況に合わせたメンタルヘルス対策を計画することが大切です。
おすすめのメンタルヘルス研修
おすすめのメンタルヘルス研修は、以下の2つです。
- 基礎知識とセルフケア手法を習得するメンタルヘルス研修
- 仕事をスムーズにし、不必要なストレスを軽減するチームビルディング研修
それぞれの研修を紹介していきます。
基礎知識とセルフケア手法を習得するメンタルヘルス研修「株式会社ノビテク」
株式会社ノビテクのメンタルヘルス研修は、メンタルヘルスに関する基礎知識とセルフケア手法を学びます。対象者は管理職、若手社員、中堅社員、新入社員で、幅広い階層の方が受講可能です。
研修は、以下のようなカリキュラムで行われます。
- はじめに
- メンタルヘルスの基礎知識を得る
- メンタル不全について考える
- セルフケアの方法について
- 私たちにできること
- まとめ
講義でメンタルヘルスに関する知識を学び、ワークで理解を深める流れです。盛りだくさんの内容ですが、研修の実施時間は約3時間なので、ビジネスパーソンに必要なメンタルヘルスの知識を効率よく身につけられます。
株式会社ノビテクは、研修を通じて基本的な方法を学んだ受講者が、うまくやり遂げるためにどうすればよいのか自分で思考できるように導く研修を主催しています。講義とワークを組み合わせ、受講者が自ら考えて行動する実践的な研修により、眠くなりにくく記憶に残りやすいプログラムが好評です。
仕事をスムーズにし、不必要なストレスを軽減するチームビルディング研修「ホリスティックサポート」
ホリスティックサポートが実施するチームビルディング研修は、メンタルヘルス研修としても活用できます。職場内での意思疎通が不十分であり、メンタルヘルスに問題を抱える会社におすすめです。
本研修の目標は、情報共有の仕組みを作って行動習慣を身につけることや、ワールド・カフェ方式のワークを通じて普段接触の少ないメンバーとの交流を促進することです。コミュニケーションを促進させることで、メンタルヘルスを健全に保ちます。
具体的な研修内容としては、以下のグループワークを通じて、問題の原因を見つけ出し、改善する手法を学びます。
- ワールド・カフェ方式のコミュニケーションワーク
- 深呼吸とマインドフルネスの実践
- 職場でもプライベートでも適用可能なマインドフルネス
グループワークでは、全員が公平に発言できる環境を設けており、部下上司関係なくコミュニケーションを図ることが可能です。
この研修を通じて、個々のメンバーがチームの一部としての役割と責任を理解し、更なるチームの連携を促進することが期待されます。その結果、組織に対して存在意義を感じられ、メンタルヘルスを保つのにも効果的です。
ホリスティックサポートは、ワールド・カフェや質問ゲームといったアクティビティ手法を活用して、オープンなアイデア会議を実施しています。部下上司関係なく、社内のコミュニケーションを促進させたい会社には、とくにおすすめです。
仕事をスムーズにし、不必要なストレスを軽減するチームビルディング研修

ワールド・カフェ方式を取り入れたコミュニケーションワークで、全員が意見を共有し、より良いチーム作りを目指します。情報共有の仕組み作りと行動習慣の改善を通じて、生産性の向上とチームの一体感を促進。職場内外で応用可能なマインドフルネスの実践も含め、多角的なアプローチでチーム力を強化します。
メンタルヘルス研修を成功させるポイント
メンタルヘルス研修を成功させるポイントは、以下の3点です。
- 自社のメンタルヘルス対策の方針を表明する
- 研修内容の見直しを定期的に行う
- 職場全体でメンタルヘルス対策を行う
自社のメンタルヘルス対策の方針を表明する
メンタルヘルス研修を成功させるためには、自社のメンタルヘルス対策の方針を表明することが重要です。
メンタルヘルス対策についての方針を表明せずに研修を行うと、社員に思うように意図が伝わらず効果的に学べません。社員に自主的にメンタルヘルス対策について学んでもらうためにも、研修前に方針を共有できていることが大切です。
たとえば、経営理念や経営方針などの企業の公的な計画書に、メンタルヘルス対策に関する理念を記載することで、社員一人ひとりの理解や協力を得られ、研修で高い効果を得られます。
メンタルヘルス研修は、企業が中心に進めるのではなく、方針を全体で共有して職員が一体となることが重要です。
研修内容の見直しを定期的に行う
メンタルヘルス研修をうまくいかせるためには、定期的な内容の見直しが必要です。メンタルヘルスによる不調の原因は、人間関係やハラスメント、業務内容など、時期によって変化します。
研修の効果を高めるには、社員に定期的にメンタルヘルスについての実施調査を行い、時期に合わせて研修計画を見なおすことが重要です。研修後には、社員から研修内容についての評価をもらい、次回の研修内容に反映させます。
たとえば「座学のみの研修が退屈だった」の意見が社員から聞かれた場合には、次回からは「グループディスカッション形式」を取り入れたり、クイズ形式にしたりなどの方法を積極的に試していきましょう。
職場全体でメンタルヘルス対策を行う
メンタルヘルス研修は、個人で実践しても効果が出るわけではなく、職場全体で実践することが大切です。研修の対策を実行するためには、環境づくりを組織全体で行う必要があります。
仮に研修で学んでも、人事部のみが実行している状態では高い効果は期待できません。現場の職場環境や、コミュニケーション方法を変えるには、各部門の管理職からの協力が必要です。管理職が、現場職員に対して仕事中に自社のメンタルヘルス対策を実行するように呼びかけを行い、職場全体への浸透を目指します。
メンタルヘルス研修は、管理職、人事部から現場の社員までが協力してはじめて効果を発揮するのです。
メンタルヘルス研修についてよくある質問
メンタルヘルス研修についてよくある質問は、以下の3点です。
- メンタルヘルス研修の効果は何ですか?
- メンタルヘルス研修の費用はいくらですか?
- メンタルヘルス研修の資料はもらえますか?
それぞれの質問に対して回答していきます。
- Q. メンタルヘルス研修の効果は何ですか?
メンタルヘルス研修を実施すると、以下の効果が期待できます。
- 働きやすい職場環境の浸透
- 社員の生産性やモチベーションの向上
- 社員の離職防止
メンタルヘルス研修を受けることで、社員一人ひとりが自身や周囲のストレス状態を把握でき、相談しやすい環境が生まれます。
その結果、働きやすい職場環境が生まれ、モチベーション向上や離職防止にもつながるのです。
- Q. メンタルヘルス研修の費用はいくらですか?
メンタルヘルス研修は「公開講義」と「講師派遣」の2種類の講義方法があり、それぞれ料金が異なります。
「公開講義」の場合では、一般的に講義時間が約3〜4時間の場合が多く、相場は1〜3万円です。講師派遣の場合も、約3〜4時間で講義が終わる場合が多く、相場は10万円前後です。
しかし、あくまで費用は相場であり、講義時間や研修の実施回数などの状況次第で料金は変動します。
また、多くの研修会社には研修前に2時間ほどの打合せや準備が必要であり、料金に含まれている場合が多いです。
- Q. メンタルヘルス研修の資料はもらえますか?
研修によっては資料をもらうことは可能です。研修会社のなかには、無料で資料請求できる企業もあります。
ただし、研修会社により異なるため、直接問い合わせるのが確実です。
メンタルヘルス研修を効果的に実施し、働きやすい職場を目指そう
今回は、メンタルヘルス研修の必要性や効果について解説しました。メンタルヘルス研修は、働きやすい職場づくり、職員のモチベーション向上や離職率の改善を目的としています。
近年では、職場での心の病が増加傾向にあり、誰もが健康でイキイキと働ける職場づくりは重要です。
メンタルヘルス研修は、知識豊富な講師にお願いするほうが高い効果を得られます。
キーセッションでは、メンタルヘルス対策に詳しい専門講師が在籍する研修会社を多数取り揃えています。その中から、予算や目的をお伺いして、最適な研修会社をご案内可能です。相談は無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。






















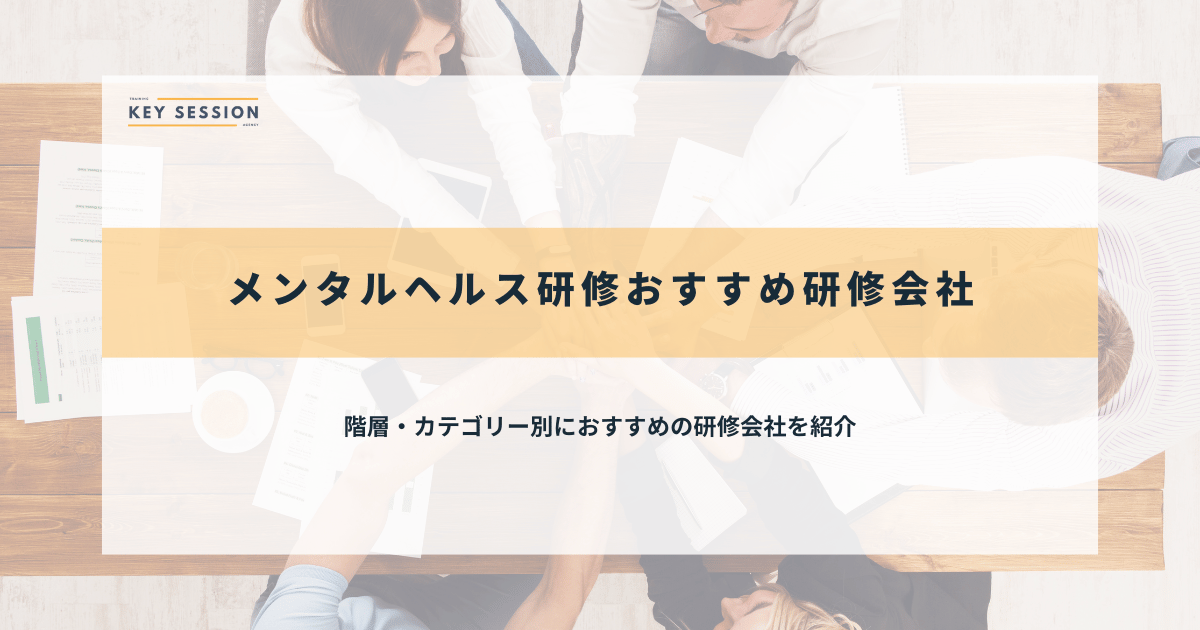 メンタルヘルス研修のおすすめ研修会社25選
メンタルヘルス研修のおすすめ研修会社25選