
SDGs研修に対して、悩みがある人事担当者や経営者も多いのではないでしょうか。
この記事では、SDGs研修の目的やプログラム・カリキュラム、費用などを紹介します。SDGs研修を検討している研修担当者は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること
- SDGs研修の目的
- SDGs研修を選ぶポイント
- おすすめのSDGs研修
SDGs研修は概念の理解や取り組み内容の策定などに、専門的な知識が求められるため、自社内での実施が難しいです。そのため、研修の実施を研修専門会社に委託するのもおすすめです。
キーセッションでは、貴社に適したSDGs研修を、さまざまなプランの中からご提案します。予算と目的を伺えれば貴社に適した提案が可能なので、お気軽にご相談ください。
目次
SDGs研修とは?
SDGs研修とは、その名の通り社員がSDGsを学ぶための研修です。
そもそもSDGsとは、経済や環境、社会問題など世界中にある17の課題を解決するためのゴールを指します。SDGsは、Sustainable Development Goalsの略で、和訳すると持続可能な開発目標です。
SDGs研修の内容は、社員がSDGsの意味を理解し会社としても貢献できるような体制を作ることです。講義やグループワークによって身近なものと感じさせ、実務にも考えが活かせるようにします。
社員がSDGsを学ぶことは、会社だけでなく顧客や社会にとっても有益で、事業の持続的成長にもつながります。
SDGs研修を行う目的
企業がSDGs研修を実施する目的は、おもに以下の4点です。
- 新規事業のチャンスを獲得
- 投資家の信頼獲得
- 企業のイメージアップ
- SDGsウォッシュの回避
それぞれを詳しく見ていきます。
新規事業のチャンス獲得
1つ目の目的は、新規事業の機会を獲得することです。
SDGsは、世界共通で意識している目標であり、持続可能なエネルギーの確保や教育機会の拡充など、壮大な問題に取り組みます。そのため、注目度が高くヒト、モノ、カネが集中しやすいです。
つまり、SDGsに取り組む過程で、新規事業の機会獲得が期待されるのです。
そのため、SDGs研修の実施を通してSDGsに本格的に取り組むことで、社会貢献と収益向上のどちらも見込まれます。
投資家の信頼獲得
2つ目の目的は、投資家の信頼獲得です。
SDGsでは、環境や社会、ガバナンスに関する各種問題を解決する目標を掲げています。企業が研修を通じてSDGsを取り入れることで、社会や環境への貢献が可能です。
各種問題の解決は経済の持続性向上につながるため、社会貢献に励む企業は投資家からの評価が高くなります。そして、そうした企業に投資する「ESG投資」が近年トレンドとなっています。
そのため、企業がSDGs活動に取り組むことは、資金調達の面で有利に働きます。獲得した資金を新規事業に投資することで、事業の中長期的な拡大が期待されるでしょう。短期的だけでなく、中長期的に利益を出せる企業は投資家からより評価されるため、いっそう投資を得られやすくなります。
企業のイメージアップ
3つ目の目的は、企業のイメージアップです。
SDGs研修の実施で、投資家の評価が高まるだけでなく、一般消費者や顧客企業にもよいイメージを与えられます。
SDGs研修では、会社の社会貢献への意識を高められます。そのため、消費者や顧客に利益を追求するだけでなく、社会貢献まで考えている企業という良いイメージを与えられます。また、実際に社会の課題を解決できれば、その効果はよりいっそう高まります。
また、会社のイメージアップによって社員自身も誇りをもつため、モチベーションや生産性向上も期待できます。会社のイメージがよいことから、求人を行った際には優秀な人材が集まりやすくなる点もメリットです。
SDGsウォッシュの回避
4つ目の目的として、SDGsウォッシュの回避が挙げられます。
SDGsウォッシュとは、SDGsに取り組んでいないのにもかかわらず、あたかも取り組んでいるかのように見せることです。実際の取り組み以上に誇張してアピールすることも、SDGsウォッシュに当てはまります。
一度発覚すると投資家や顧客からの信頼を失ってしまうため、SDGsウォッシュは避けなければいけません。
ただし、知識の浅いまま自分たちでSDGs研修を実施しても、目的や重要性を理解しきれずSDGsウォッシュが起こりかねません。回避のためにも外部の専門家や研修会社に研修を依頼するのがおすすめです。
企業が抱えるSDGsの悩み・課題
SDGsは持続可能な社会のため、世界全体で取り組む必要のある課題です。日本国内でもSDGsの認知度は高まり、積極的に取り組みを行っている企業が増えています。しかし、以下のような悩みや課題があり、遅れを取っている企業が多いことは否めません。
- 社員がSDGsを理解していない
- SDGsに取り組む必要性に疑問がある
- 企業にできることは限られている
- 自社の事業とSDGsがどのように結びつくのかわからない
- CSRや社会貢献との違いがわからない
SDGsという用語の意味を知っているだけでは、本質的な理解ができていないので、このような疑問が生まれてしまいます。SDGsの本質や企業として取り組むことの意義を理解してもらうためにも、SDGs研修を導入して社内に知識を普及させましょう。
SDGs研修の対象者
SDGs研修の対象者は、新入社員から経営者まで、すべての階層の社員です。どのような階層の社員でも、一度は受講しましょう。
ただし、SDGsに対して身につけるべき知識は、階層によって異なります。経営者の場合、SDGsをビジネスチャンスとして捉えて新規事業を創出するといった、経営の舵取りをするための知識が必要です。
一方、新入社員が研修を受講する場合、経営の舵取りを教えるのはミスマッチです。現在の世界はどのような問題を抱えており、長い目で見たときの世界の将来像を学べる研修をおすすめします。
受講者の階層に合わせ、SDGs研修をカスタマイズすると効果的です。
SDGs研修のカリキュラム例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入 | ◆SDGsの基礎知識 ・SDGsとは何か(歴史・注目される背景) ・なぜ企業がSDGsに取り組まなければならないのか ・SDGsに取り組むメリットとは |
| SDGsと自社のビジネスとの関係性 | ◆ビジネス事例の解説 ・SDGsとビジネスとを結びつけた成功事例 ◆ワーク:「2030SDGs」カードゲーム ・SDGsの17目標を2030年までに達成する道のりを体験できるゲームを実施 |
| 自社のSDGs戦略を立てる | ◆ワーク:自社事業とSDGsを結びつける ・自社の強みとSDGsの各目標を照らし合わせ、既存事業の発展や新規事業の創出を行う |
| まとめ | ◆サスティナブルな企業経営とは ◆ワーク:明日から社内で実施するSDGsの取り組みを目標設定 |
SDGs研修のカリキュラム例は、以下の通りです。
- SDGsの基礎知識
- ビジネス事例の解説
- 自社事業とSDGsを結びつけるワーク
それぞれを具体的に見ていきます。
SDGsの基礎知識
まず、SDGsの基礎知識を学びます。具体的な基礎知識は、以下の3つです。
- SDGsとはなにか(歴史や注目される背景)
- なぜ企業がSDGsに取り組まなければならないのか
- SDGsに取り組むメリットとは
SDGsの意味や注目される理由、企業にとってのメリットなど、さまざまな知識を学びます。基礎知識が無ければ研修をする意味も見出せないため、しっかり行いましょう。
ビジネス事例の解説
次に、ビジネス事例の解説を実施します。
事例を学ぶことで、社員がSDGsとビジネスの関係を具体的にイメージできます。事例を学ぶことで、SDGsとビジネスが両立できる理由やメリットが理解できるため、研修において大切なポイントです。
また、2030SDGsカードゲームの利用もおすすめです。2030年までに目標達成をするための道のりを、ゲーム感覚で学べます。
自社事業とSDGsを結びつけるワーク
最後に、自社事業とSDGsを結びつけるワークを実施します。
実際に自社事業とSDGsを結びつけて、既存事業の発展や新規事業を創出するワークがおすすめです。自社において、SDGsをどう活かせるかの視点を養えます。
また、まとめのワークでは、翌日から会社で実施できるSDGsと目標設定をしましょう。
SDGs研修を成功させるポイント
SDGs研修の成功に必要なポイントは、以下の3点です。
- 階層別の研修を行う
- 座学だけでなくワークも行う
- 研修の目的を決定する
それぞれを詳しく解説していきます。
階層別の研修を行う
社員数が多い企業の場合、階層別にSDGs研修を行いましょう。SDGsへの取り組み方は、経営層・幹部・社員・新入社員など立場によって異なるからです。
経営のかじ取りを行う経営層と、現場で商品やサービスを提供する社員とでは、実務の内容が異なります。各階層に必要な知識を学んでもらうためにも、それぞれに適した研修内容で実施しましょう。
座学だけでなくワークも行う
SDGsの基礎知識を座学で学んだ後、自社事業とSDGsをどのように結びつけたらよいのか考えるワークを行いましょう。研修会社に依頼する場合、座学のみやワークなしプログラムのケースもあります。
ワークを行うことで、自社のビジネスでSDGsを達成するための方法を、社員が身につけられます。能動的にSDGsとビジネスに取り組む社員を育てるためにも、ワークを導入しましょう。
研修の目的を決定する
目的を決定することは、研修を成功させるうえで重要なポイントです。研修効果測定や研修実施の社内承認を取る際などには、目的が必要です。
「SDGsの観点から自社の課題を抽出できるようにする」、「自社事業とSDGsを結びつけられるレベルにする」など、目的は具体的に決めましょう。
また、研修を提供する企業側から見ても、明確な目的があれば的確なプランやサービスを提供できます。すり合わせることで工数の削減や、プランのブラッシュアップに時間がかけられるなどのメリットもあるため、目的を決めましょう。
SDGs研修を選ぶポイント
SDGs研修を選ぶポイントは、以下の2つが挙げられます。
- 他社事例に強いか
- ワークを導入しているか
それぞれ詳しく見ていきます。
他社事例に強いか
座学の中で、他社事例を豊富に紹介してくれる研修を選びましょう。抽象的な基礎知識に加え、実践的な具体例を学ぶことで、実際のビジネスに応用できる考え方を養えるからです。
SDGsについての知識を解説するだけの研修だと、知識は身についても社員は実践できる力を身につけられません。他社ではどのようにSDGsとビジネスを結びつけているのか、詳しく解説してくれる研修を選びましょう。
ワークを導入しているか
SDGsと自社のビジネスを結びつける能動的なワークを導入している研修を選びましょう。SDGs研修の中には、座学のみ・ワークなしの研修もあります。しかし、ワークが無いと社員は、主体的にSDGsやビジネスの創出に取り組むための力を身につけられないからです。
自社の強みを分析し、SDGsのゴールをビジネスチャンスとして新規事業のアイディアを出すワークを行う研修を導入することで、企業の経営力を向上させられます。
おすすめのSDGs研修
おすすめのSDGs研修は、以下の2つです。
- 組織の壁を越える!コラボレーション力強化リトリート研修
- 自然の中で学ぶ!自然体験型研修でチーム力を向上させる
それぞれ、具体的に見ていきます。
組織の壁を越える!コラボレーション力強化リトリート研修「亀山温泉リトリート」
亀山温泉リトリートでは、SDGsの知識や組織力、コラボレーション力を高めるための研修を実施できます。新規事業でチームのコミュニケーションを高めたい場合や、部下のモチベーションを上げたい場合などにおすすめです。
プログラム内容は、薪割りや焚火、ヨガ、ネイチャーガイドなど自然体験を含めていることが特徴です。自然の中で行うチームビルディング活動によって、組織力が高まる研修が実施できます。プログラム内容も自由に変更できるため、気軽に利用しやすいです。
また、SDGsの第15目標である陸の豊かさを守ることにもつながる研修が受けられます。人と自然が共栄していく方法を学び、さまざまな役割や性格の人と共存していくスキルが習得可能です。
亀山温泉リトリートは、自然をテーマにしたリトリート研修を用意しています。セミナーや合宿、研修などさまざまな用途に合わせられることが特徴です。
奥房総・亀山温泉でのSDGs活動、山の風倒木整備や薪割り&焚き火体験、湖畔ヨガなど自然体験を通じて異部署の壁を越え、新規事業への主体的参画も促し、コミュニケーション促進とチーム一体感を高め、持続可能な組織文化を育むコラボレーション力強化リトリート研修。
自然の中で学ぶ!自然体験型研修でチーム力を向上させる「亀山温泉リトリート」
亀山温泉リトリートのこちらの研修では、SDGsへの理解を深めつつも、自然体験型の研修を用いてチームビルディングを高められます。研修プログラムにはヨガや歩き方なども含まれるため、社員の健康意識向上が期待できることも魅力です。
オリエンテーションから始まり、アクティビティや集中研修などでチーム力やSDGsへの関心を高めます。研修の目的に合わせたり、アクティビティの有無を決めたりできたりと自由度も高いため、気軽に利用できます。
宿泊施設も設置されているため、日帰りではなく複数日にわたっての研修も実施可能です。
自然豊かな亀山温泉リトリートで、風倒木整備や焚き火体験、ヨガ、SDGs活動を通じチームビルディング、コミュニケーション強化、健康意識向上を図り、新規事業推進やセクショナリズム解消、新入社員フォローアップにも最適な研修プランで組織の一体感を醸成し、持続可能な成長を促進。
SDGsとCSR、ISO14001、ESGとの違い
SDGsと類似する概念にはCSR、ISO14001、ESGがあります。SDGsとの違いは以下の通りです。
- SDGsとCSRの違いは、社会的な取り組みかボランティアか
- SDGsとISO14001の違いは、目標か国際規格か
- SDGsとESGの違いは、社会としての取り組みか企業としての取り組みか
それぞれを詳しく解説していきます。
SDGsとCSRの違いは、社会的な取り組みかボランティアか
SDGsとCSRの違いは、社会的な取り組みかボランティアかです。
SDGsは、ビジネスを通じて環境問題や社会問題など、17の開発目標を達成していく取り組みです。一方CSRとは、環境への配慮だけでなく、社員や投資家など利害関係のある人に対しての社会的な責任を指します。
CSRに取り組むことでも、社会への貢献や社会的責任を果たせます。ただし、CSRだけでは不十分な場合があり、SDGsに取り組むことで継続してビジネスと社会貢献の両立が可能です。
SDGsとISO14001の違いは、目標か国際規格か
SDGsとISO14001は、目標か国際規格かの違いです。そのため、審査や達成期限の有無にも違いがあります。
SDGsの場合はどんな企業でも参加できますが、ISO14001は審査を通らなければいけません。達成期限は、SDGsが2030年まで(出典:外務省)と決まっていますが、ISO14001は明確には定められていません。
また、対象はSDGsが先進国から開発途上国までなのに対し、ISO14001は自治体や企業です。
SDGsとESGの違いは、社会としての取り組みか企業としての取り組みか
SDGsとESGの違いは、社会としての取り組みか、企業としての取り組みかです。
SDGsでは、環境問題や経済問題など、社会として目標達成に向かって活動します。ESGでは、社会ではなく企業として、株主や投資家への説明に取り組みます。
SDGs研修についてよくある質問
SDGs研修についてよくある質問は、以下の4つが挙げられます。
- 自社の現状に合わせたカスタマイズは可能か
- 研修だけでなく、アフターサポートもしてもらえるか
- オンラインでの研修は可能か
- 研修期間・費用はどの程度か
それぞれを詳しくチェックします。
- Q. 自社の現状に合わせたカスタマイズは可能か
- 企業によりますが、カスタマイズは可能です。導入企業の課題や、現状に合わせたプログラムを作成できます。効果的な研修を行うため、SDGsとして取り組んでいることやコンプライアンス、社会貢献の取り組みなど、現状を研修会社にお聞かせください。また、受講者のレベルによっても、SDGs研修で身につけるべき知識は異なります。受講者の階層や立場に応じてプログラムをカスタマイズできるので、お気軽にご相談ください。
- Q. 研修だけでなく、アフターサポートもしてもらえるか
- 事前に相談しておけば、アフターサポートもしてもらえることが多いです。継続的な研修だけではなく、コンサルティングも可能です。SDGs研修には、SDGsの普及を目的としている企業が提供するプログラムと、研修専門会社が提供するプログラムがあります。前者の場合、研修からコンサルティングまで同じ企業に実施してもらえます。後者の場合は別の会社に分かれますが、他の研修もセットで実施できることがメリットです。
- Q. オンラインでの研修は可能か
- ほとんどの場合、オンラインでの受講が可能です。SDGsを基礎から学べる配信動画を活用したeラーニングを使い、時間や場所を問わず受講できます。ただし、カードゲームを用いた研修など、集合研修でなければ受講できないプログラムもあります。集合研修とオンライン研修のどちらがより効果的であるかは、企業の現状や受講者のレベルによってバラバラです。どのような形式が最適なのか、研修会社に相談してみましょう。
- Q. 研修期間・費用はどの程度か
- オンラインとオフライン(集合研修)では、大まかな目安が異なります。オンラインの場合は、提供される動画のボリュームによって期間や時間は変動します。オフラインの場合は、数時間程度から数日間程度までさまざまです。オンラインの費用は、3万円から15万円程度です。オフラインの費用は、1日につき10万円から20万円程度かかります。
SDGs研修を実施して、自社の事業拡大につなげよう
SDGs研修の目的は、新規事業のチャンス獲得や企業のイメージアップなどさまざまです。研修を成功させるには、ワークを実施したり目的を決定したりとポイントを押さえておきましょう。
SDGs研修を選ぶ際は、他社事例に強いかとワークを導入しているかの2点に注意することが大切です。オンラインとオフラインで、期間や費用が異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、研修担当者の中には、通常業務が忙しくSDGs研修の準備が進まない人も多いです。そこで、研修の実施を研修専門会社に任せる方法もおすすめです。
キーセッションでは、貴社に最適な研修を、豊富な研修プランから提案できます。相談無料で、予算と目的だけで提案できるので、お気軽にご相談ください。
KeySessionでは貴社のSDGs研修導入をお手伝いをいたします。







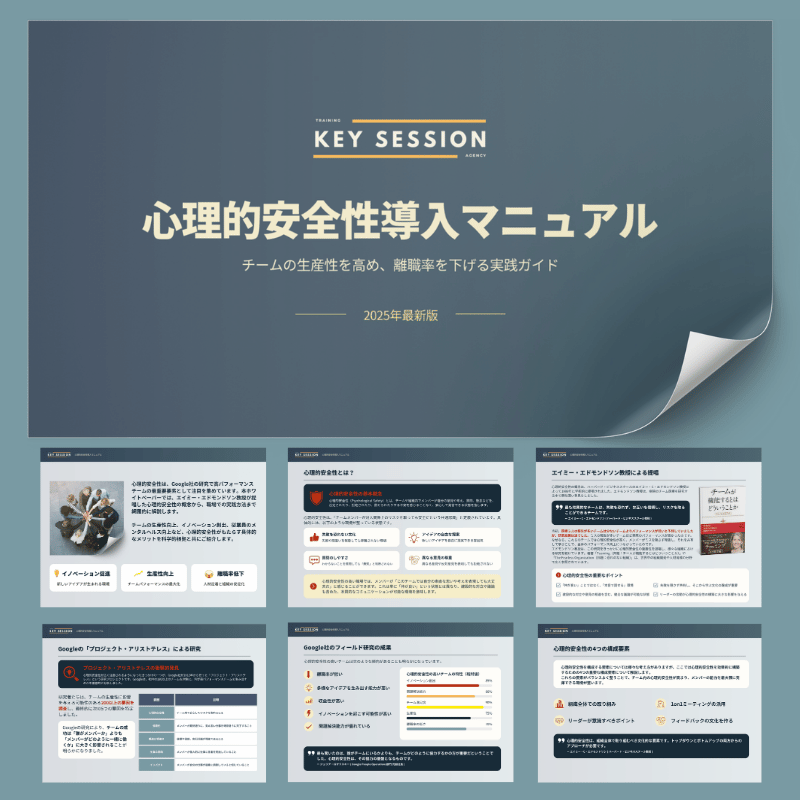



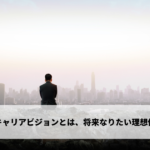

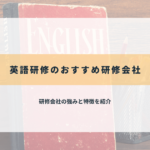
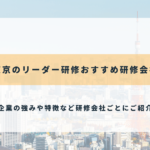
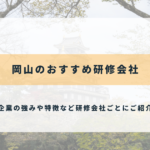
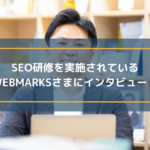
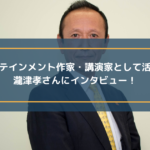

 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート