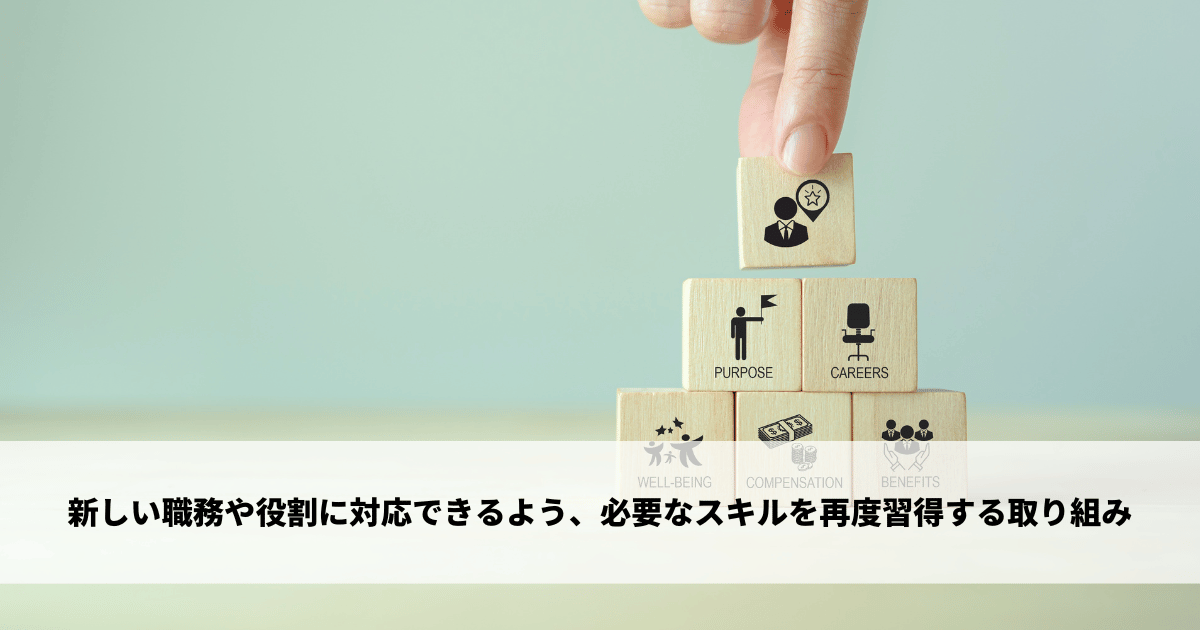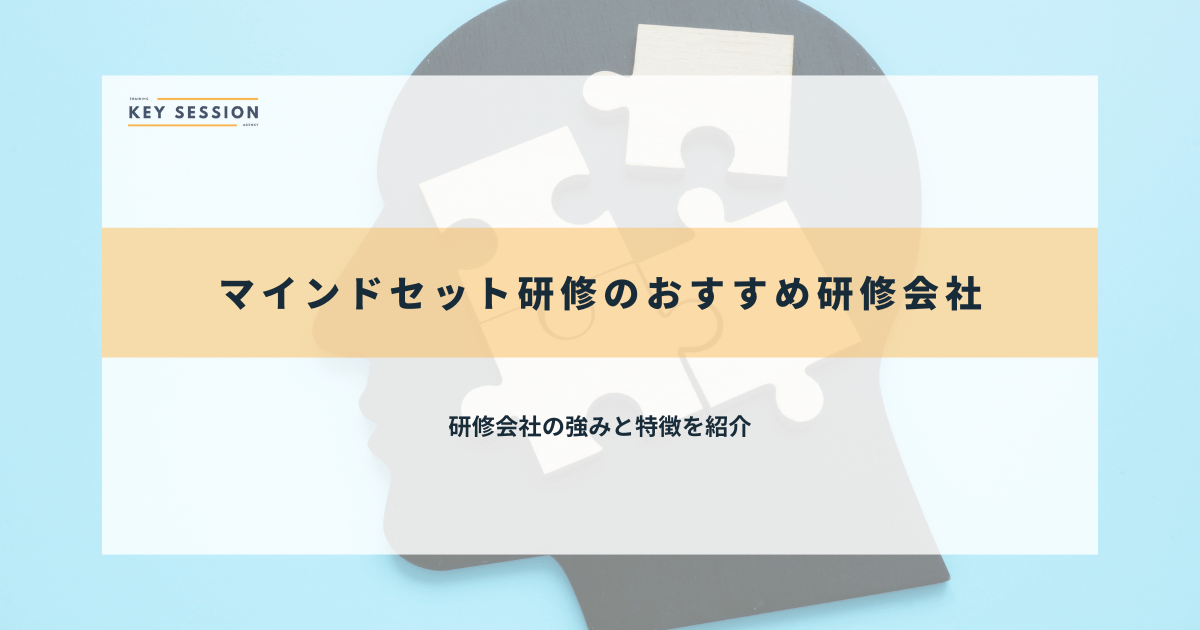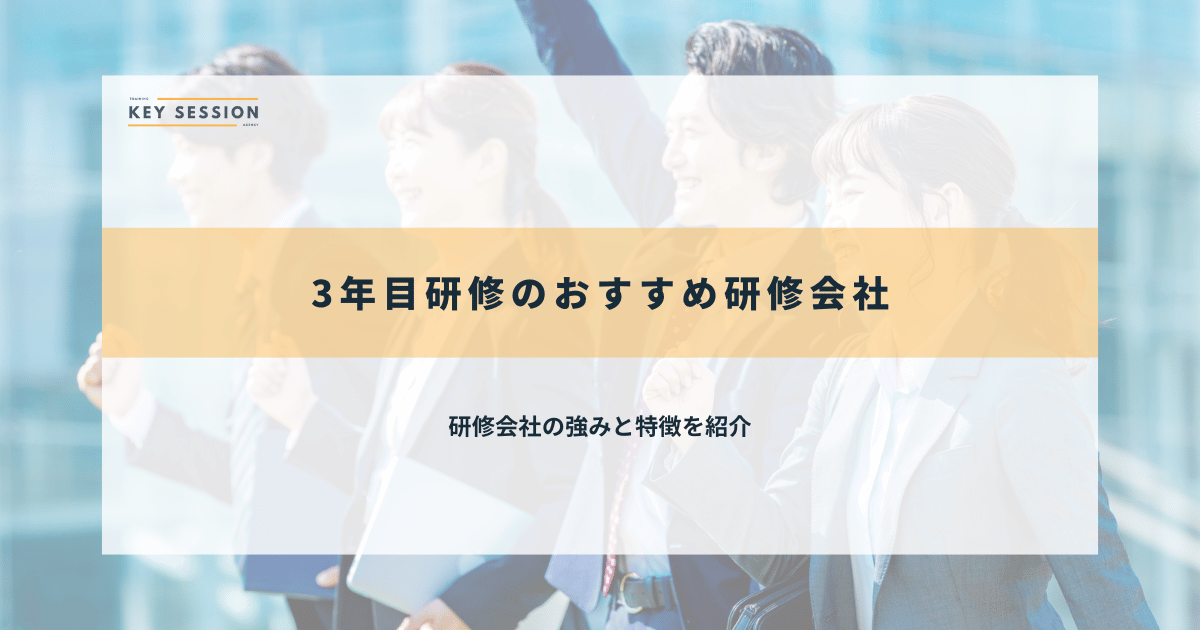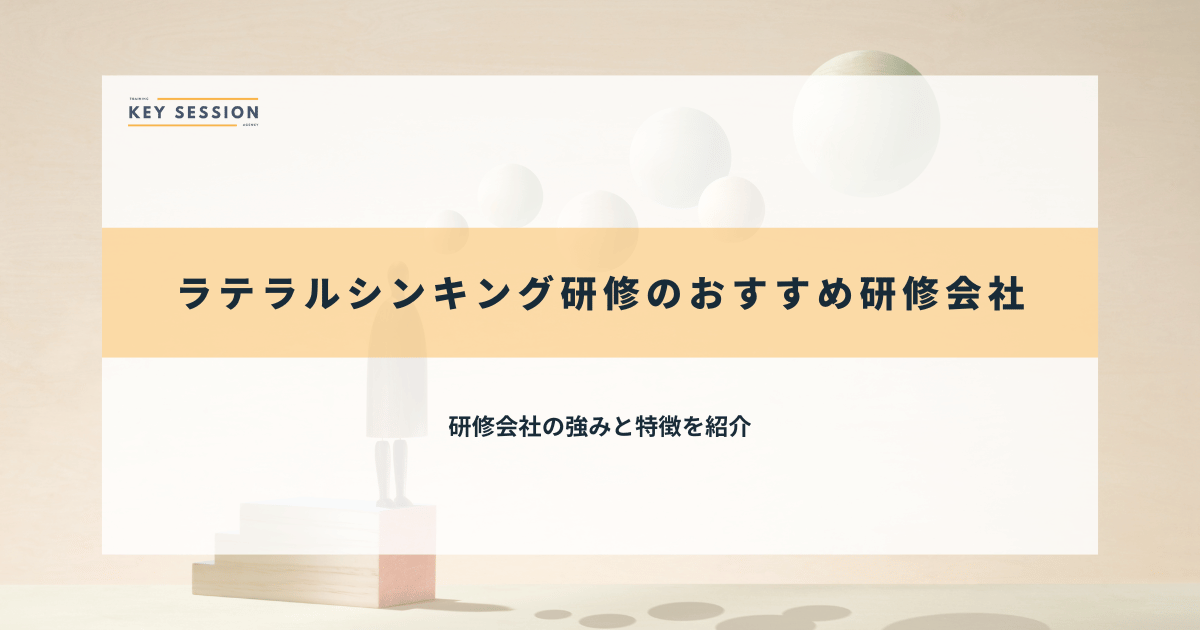「クリティカルシンキングを研修で社員に浸透させたい」「他社がクリティカルシンキング研修をしていたので自社でもやりたいが、どの研修がおすすめかわからない」
このような悩みを抱えている経営者や人事担当者もいるのではないでしょうか。
当記事では、クリティカルシンキング研修の概要や受講するメリット、費用、選ぶ際のポイントについて紹介していきます。
クリティカルシンキング研修を検討している方は、ぜひご一読ください。
この記事でわかること
- クリティカルシンキング研修を実施するメリット
- クリティカルシンキング研修の費用
- クリティカルシンキング研修を選ぶ際のポイント
結論からお伝えすると、クリティカルシンキング研修を選ぶ際は、研修内容や講師の質が重要です。キーセッションは複数の研修会社の中から、貴社のご要望にあわせて最適な研修会社をご提案します。ご相談は無料なので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

クリティカルシンキング研修とは
クリティカルシンキング研修とは、論理的思考力や問題解決能力を身につけられるクリティカルシンキングについて学ぶ研修です。
研修では、まずはクリティカルシンキングとは何か、その定義や考え方を学びます。一通り座学で学んだら、今度はディベートや第三者目線で自分と向き合うワークなど、より実践的な研修に移ります。
クリティカルシンキングとは
クリティカルシンキングとは、前提や根拠を疑うことによって、課題を解決する思考プロセスです。この手法では、自分が無意識にとらわれている固定観念を一度取り払い、客観的立場で物事を分析することで、正しい結論へと迫ります。
たとえば、ホテルマンが宿泊者の部屋を無償で上層階にアップグレードした際に、相手からクレームを受けたとします。一般的には、眺望のよい上層階の部屋は人気があり喜ばれますが、人によってはその常識が当てはまりません。
もしも宿泊者がすぐ外に出られる利便性の高い低層階を希望していたり、高所恐怖症だったりした場合には、ホテルマンの対応ははた迷惑そのものです。このようなクレームには、本質を見抜くクリティカルシンキングの手法で対応するのが有効です。
なお、クリティカルシンキングは日本語では「批判的思考」と訳されます。しかしここでいう批判とは、否定や非難を意味するものではなく、理性的かつ中立的に物事を判定することを指します。
ネガティブな意味合いは含まれておらず、もちろん相手をやり込める手法でもないため、誤解の無いように注意しましょう。
クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違い
クリティカルシンキングとロジカルシンキングは、どちらも問題解決や意思決定において重要な思考プロセスですが、結論を出すまでのプロセスが異なります。
上述したように、クリティカルシンキングでは思考プロセスの最初の段階で、まずは与えられた前提条件や無意識な思い込み、直観などをすべて取り払うところからスタートします。
一方でロジカルシンキングは、一貫した論理にもとづいて物事を整理する手法です。課題や問題に対し要素を細分化のうえ、矛盾が無いよう筋道を立てて考えを構築していきます。
つまり、ロジカルシンキングがある前提にもとづいて思考を組み立てていくのに対し、クリティカルシンキングは前提そのものの妥当性を試行錯誤しながら検証していく違いがあります。
なおロジカルシンキングの研修は、以下のページで解説しています。
クリティカルシンキングの必要性
クリティカルシンキングは、多様化する社会で勝ち抜くために、習得すべき思考プロセスです。
昨今では、働き方改革やパンデミックなどの影響も相まって、世の中の価値観は多様化しています。異なる考え方や価値観をもつ人が増えるにつれ、これまでの常識が通用しなくなってきているのです。
このような背景から、従来の型にはまった考えから脱却可能な問題解決法が必要とされます。クリティカルシンキングは、多様化する時代に則したうってつけの思考プロセスといえます。
クリティカルシンキング研修の対象者
クリティカルシンキング研修の対象者は、とくに限定されていません。以下のような幅広い階層の社員を対象としています。
- 新入社員
- 中堅社員
- 管理職
- 経営層
一般的にクリティカルシンキング研修は、中堅社員が多く受講している傾向がありますが、どのような階層の社員でも受講しておく価値があります。
クリティカルシンキング研修を実施するメリット
クリティカルシンキング研修を受講するメリットは、以下の4点です。
- 論理的思考力の向上
- 問題解決能力の強化
- コミュニケーション力の向上
- 新しいアイデアの創出
それぞれ解説していきます。
論理的思考力の向上
クリティカルシンキング研修を実施すれば、対象社員やチームメンバーの論理的思考力向上が見込めます。
クリティカルシンキングは、主観を排除して思考することで、物事の本質にせまるメソッドです。客観的視点に立ちながらデータを精査し、思考を重ねることで、論理にもとづいた的確な判断が下せます。
結果、事実を根拠とした「論理的に物事をとらえる力」が強化されます。
問題解決能力の強化
クリティカルシンキング研修の実施によって、問題解決能力の強化を図れるメリットもあります。
クリティカルシンキングは、考えるべきことの漏れを防ぎつつ、物事の矛盾を洗い出す優れた手法です。身につければ物事を深く掘り下げられるようになるため、問題解決に役立ちます。
クリティカルシンキングは、別の問題解決方法の欠点を補うのにも有効です。
コミュニケーション力の向上
クリティカルシンキング研修の実施によって、社員同士のコミュニケーション力の向上が見込める点も大きなメリットです。
クリティカルシンキングによって物事を客観視し、相手との認識のズレを埋めることで、相手の話を容易に理解できます。また、相手の意図を把握することで自分の意図も相手に伝わりやすくなり、自分の主張に説得力が生まれる利点もあります。
感情論に陥らず、事実に基づき中立的な立場で議論を進められるため、円滑なコミュニケーションが可能です。
新しいアイデアの創出
クリティカルシンキング研修を実施すれば、新しいアイデアの創出にもつながります。
前提条件を疑ってみることで、新たな気付きが得られる場合も少なくありません。クリティカルシンキングで物事に対し多角的なアプローチができれば、従来まででは到達しえなかった考えにたどり着く可能性があります。
結果、これまでとは違った問題解決策が得られたり、まったく新しい商品の開発に成功したりする場合があります。

クリティカルシンキング研修の費用
クリティカルシンキング研修の費用は、研修内容や形式、提供会社によって大きく異なります。以下3つの形式別で、費用相場を紹介していきます。
- オンライン研修
- グループ研修
- 個別コンサルティング
オンラインで提供されるクリティカルシンキング研修は、費用が比較的安価な場合が多く、数千円から数万円程度で受講可能です。
企業や組織向けに提供されるグループ研修は、参加者数や研修内容によって費用が異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度の費用がかかります。
クリティカルシンキング研修を個別に受ける場合、コンサルタントの経験や実績によって費用が大きく異なりますが、数万円から数十万円程度の費用がかかるのが一般的です。
| 研修の種類 | 費用相場目安 |
|---|---|
| オンライン研修 | 数千円~数万円程度 |
| グループ研修 | 数十万円~数百万円程度 |
| 個別コンサルティング | 数万円~数十万円程度 |
クリティカルシンキング研修のカリキュラム例
クリティカルシンキング研修のカリキュラム例は、以下の通りです。| 日程 | 内容 | ゴール |
|---|---|---|
| 1日目午前 | クリティカルシンキングとその重要性 | 【講義】クリティカルシンキングとは? クリティカルシンキングができなければどうなるか?を理解し、自発的に行う必要性を理解、納得 【講義】ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違いを把握し関係を理解し活用する 【演習】このプレゼンは妥当か?を検証し「自分ならどうするか?」をアウトプットし活用イメージを高める 【演習】ロジカルシンキングを使い検討し活用イメージを高める |
| 1日目午後 | クリティカルシンキングの重要技法 | 【講義・ケース】前提を疑う思考と思考の癖を学び、ケースを通じて深める 【講義・ケース】PAC思考についてを学び、「自分だったらどうするか?」を考え、自分で考える力を養う |
| 2日目午前 | 解決策の明確化 | 【講義】解決策を提示するまでの流れを理解する 【ケース】いつも発生する職場の問題とその解決策を考える |
| 2日目午後 | 総合演習 | 【ケーススタディ】あなたならこの問題をどう解決するか?で解決力を強化する 【ケーススタディ】あなたが考える、当社の3年後目標達成のために必要となる課題を設定し解決策を整理する |
おすすめのクリティカルシンキング研修
おすすめのクリティカルシンキング研修としては、株式会社モチベーション&コミュニケーションの研修プランが挙げられます。同社では、「ビジネスで成果を上げていくためのクリティカルシンキング研修」を実施しています。
この研修は、クリティカルシンキングそもそもの定義の解説からはじまり、演習をメインにした講義を行うものです。研修内では、事実や意見の違いの見極め方、前提条件の疑い方、結果を精査する方法などを、実例を交えつつ体系的に学んでいきます。
研修を実施する企業に合わせて研修内容をカスタマイズ可能なので、自社の実情に則した研修によって実践に活かせるメリットがあります。

上司と部下のコミュニケーションを改善し、事実と意見を区別してズレを解消。前提を問い直し本質を素早く捉える思考力を演習で磨き、論理的判断と自信を醸成。日々の業務での意思決定をスピードアップし、部下からの報連相の質向上も実現。生産性とチーム力を継続的に高める研修です。
クリティカルシンキング研修を選ぶ際のポイント
クリティカルシンキング研修を選ぶ際のポイントは、以下の3点です。
- 研修の目的に沿って選ぶ
- 理論と実践のバランスが取れている研修を選ぶ
- 講師の質を確認する
具体的に解説していきます。
研修の目的に沿って選ぶ
クリティカルシンキング研修を選ぶ際には、研修の目的に沿って選ぶのがポイントです。たとえば、以下のような目的が想定されます。
- クリティカルシンキングの基礎を学ぶ
- 実務でクリティカルシンキングを使えるようにする
前者の場合であれば、比較的どのような研修でも適しています。研修会社との相性や予算などを重視して選んでもかまいません。
後者の場合であれば、オーダーメイドができたり、多数の例題を保有している研修会社を選ぶのがおすすめです。せっかく研修で学ぶのであれば、実務で使えるようにしてみてはいかがでしょうか。
理論と実践のバランスが取れている研修を選ぶ
クリティカルシンキング研修は、座学と演習で構成されるのが一般的ですが、理論と実践のバランスが取れている研修を選ぶのもポイントです。
基本的な理論がわからなければ、クリティカルシンキングの意義や活用方法などが判然としないまま研修が終了してしまいます。一方、研修中に実践的なケーススタディが十分体験できなければ、知識の定着が進まず、現場で活用できる生きたノウハウも身につきません。
一般的には、実践に重きを置いている研修のほうが高い効果を期待できます。座学でいくら理論を学んでも、実践の機会が無いとクリティカルシンキングの使い方がわからないからです。
座学と実践のバランスは研修会社によって異なり、どのようなバランスが最適であるかは導入企業のニーズによっても異なります。自社のケースに落とし込んで研修バランスを検討するのが肝要です。
講師の質を確認する
クリティカルシンキング研修を選ぶ際には、講師の質を確認することがポイントです。講師の質によって、研修の効果が左右されるからです。
経験豊富な講師に依頼すれば、受講者がつまずきやすい点に配慮した指導を行うことで、現場で活かせる実践的なノウハウが身につきます。
キーセッションでは、質の高い講師による研修をご案内しています。クリティカルシンキング研修を検討されている方は、ぜひキーセッションにご相談ください。
クリティカルシンキング研修についてよくある質問
クリティカルシンキング研修についてよくある質問は、以下の2点です。
- 短時間で研修を実施できますか?
- クリティカルシンキング研修とセットで実施すると効果的な研修はありますか?
それぞれ回答していきます。
- Q. 短時間で研修を実施できますか?
研修会社は導入企業の要望に合わせてカリキュラムを作成するので、希望する時間で研修の実施が可能です。
ただし、1~2時間などあまりにも短い時間だと、充分にクリティカルシンキングが身につかない可能性があります。座学で理論を学び、実践を何度か繰り返してスキルを定着させるためには、ある程度の時間が必要です。
集合研修に時間が割けない場合は、事前にeラーニングで基礎知識を学んでおき、集合研修ではグループワークのみを実施する方法がおすすめです。要望に合わせ最大限の効果を発揮できるよう、研修会社が研修内容や研修時間を調整するので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
- Q. クリティカルシンキング研修とセットで導入すると効果的な研修はありますか?
クリティカルシンキング研修とあわせて、ロジカルシンキング研修やラテラルシンキング研修を導入すると効果的です。
ロジカルシンキング研修は論理的思考力を身につけられる研修で、ラテラルシンキング研修は柔軟な発想で思考の幅を広げられる研修です。これらの思考方法は一見似ていますが、本質が異なります。
3つの思考方法を理解し実践すれば、前例の無い新規のアイディアが生まれ、柔軟な思考で既存のビジネスの見直しが可能です。
クリティカルシンキング研修で組織全体の課題解決力をアップ
クリティカルシンキングを身につければ、論理的思考力が向上し、これまでに無かった斬新なアイデアも導き出せます。企業研修に取り入れれば、組織全体の課題解決力アップが期待できます。
ぜひクリティカルシンキング研修を実施し、自社の利益に結び付けましょう。
キーセッションでは、クリティカルシンキングのスキルを効率的に身につけられる研修をご案内しています。貴社に合った研修内容にカスタマイズ可能な研修会社を紹介しているので、研修を検討中の方はぜひキーセッションにご相談ください。





















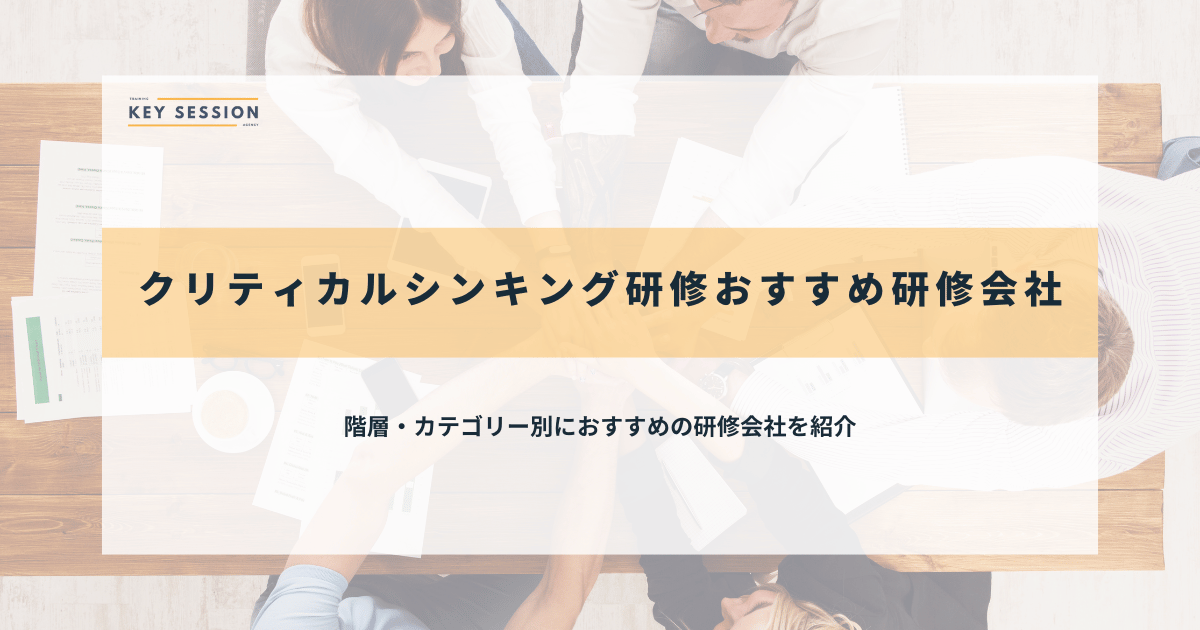 クリティカルシンキング研修のおすすめ研修会社16選
クリティカルシンキング研修のおすすめ研修会社16選