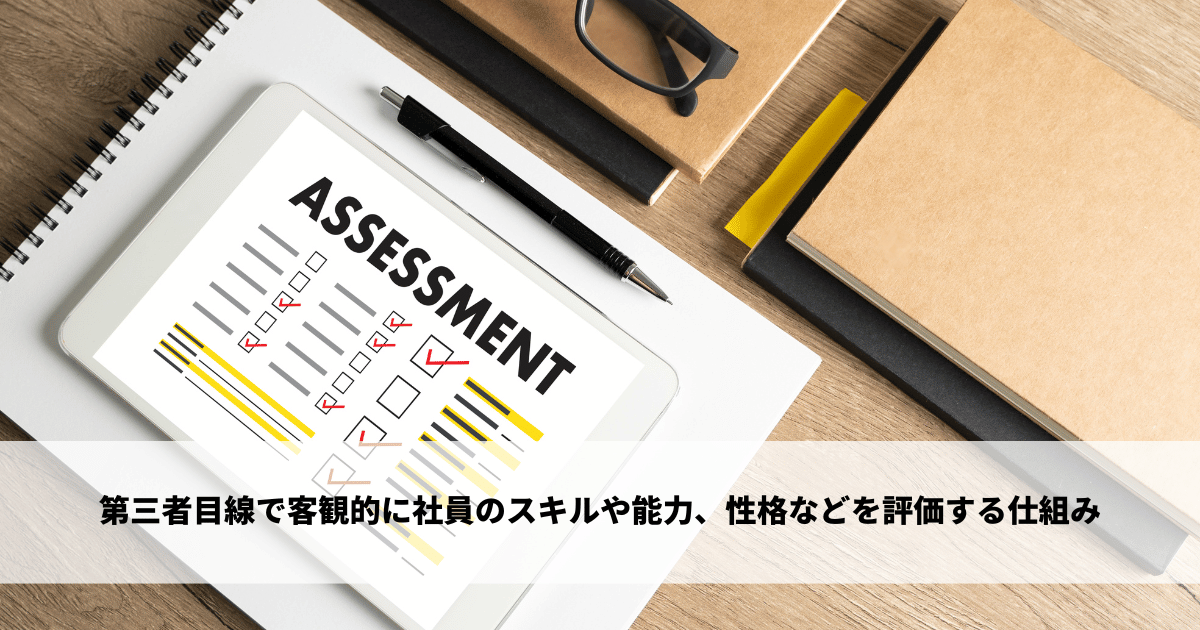
目次
人材アセスメントとは?
人材アセスメントとは、第三者目線で客観的に社員のスキルや能力、性格などを評価する仕組みです。報酬の決定に用いられる人事評価とは違い、社員の能力開発や人員配置の参考とすることが多いでしょう。
人材アセスメントの特徴を詳しく理解するために、「人事評価」や「組織アセスメント」といった類似した概念との違いを解説します。
人事評価との違い
人事評価は、社員の業績や成果を評価して報酬や等級を決定することを指します。社員に対して評価を行う点は人材アセスメントと同じですが、評価方法や目的が異なります。
人材アセスメントによる評価は、基本的には社外のツールや人間によって行うことが特徴です。適性検査や研修、スキルチェックなどを通して、客観的に評価します。一方で、直属の上司が行う人事評価は、主観によって評価が偏る可能性があります。
また、人材アセスメントの目的は、社員のスキルや適性を可視化し、適材適所への配置やリーダーの選抜などに役立てることです。あくまでも人材戦略のために行われるもので、報酬が決定する人事評価とは目的が異なります。
組織アセスメントとの違い
組織アセスメントとは、企業全体の特徴や現状を評価することであり、人材アセスメントよりも包括的な評価を指します。組織アセスメントにより、自社にどのようなスキルや性格、適性がある社員が多いかを把握でき、人材戦略を立てやすくなるでしょう。
例えば、ある会社が「先進的なプロジェクトの推進」というビジョンがあり、リーダー気質の社員が少ないことが判明したとします。その結果から、リーダーの育成や採用に注力するというように、課題への対策が明らかになるでしょう。
能力やスキルを客観的に評価する点は同じですが、組織か個人か、どちらに焦点を当てるかが異なります。組織と個人の両面に対してアセスメントを行うことで、組織としての課題や対応策がより明確になります。
人材アセスメントが重視される理由
客観的で個人に焦点を当てた評価方法として、人材アセスメントは重視されています。組織の人材戦略に役立つ視点だといえますが、どのような理由から重視されているのでしょうか。
1.個人の多様性に対応するため
人材アセスメントは、グローバル化や働き方の変化に伴う、個人の多様性に対応するために重要です。昨今では、終身雇用制や年功序列制度が崩壊したり、管理職への昇進を望まない若手がいたりするなど、社員のニーズや働き方が多様化しています。
また、グローバル化に伴う競争の激化と人材不足により、社員の適性に応じた配置を行い、能力を十二分に発揮する施策が必要です。
変化する社会構造の中では、組織における「有能な人物像」も多様化しているといえるでしょう。そのため、全社員に対する画一的な評価ではなく、多面的な評価方法が必要です。その方法の一つとして、人材アセスメントが求められているのです。
2.働き方の変化により評価がしにくくなったため
新型コロナウイルスの感染拡大以降、リモートワークを導入する企業が増加し、社員同士が対面で接する機会が減少しました。管理職は、部下のことを十分に知らず、正当に評価しにくいというケースが増加しています。
働き方の変化により、客観的な評価をもとに人材の適正配置を行うことが重視されています。
人材アセスメントを導入するメリット
個人に注目し、人材配置の適正化につながる人材アセスメントですが、導入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
1.ミスマッチ防止により定着率が向上する
人材アセスメントにより、採用や配属時のミスマッチを防止できるでしょう。採用試験の際に人材アセスメントを実施することで、適性や性格、能力を正確に把握できます。自社が求める人材を獲得でき、社員も適性を生かして働けるため、定着率が向上するでしょう。
2.人材育成・研修の効果が上昇する
社員一人ひとりの能力や特性を把握するのが人材アセスメントの役割です。自社が求める人材要件への過不足が明確になり、研修の目的や対象者が具体化されるでしょう。
また、教育効果を測るために定期的に実施することも有効です。実施している教育が効果的かを検証し、計画を修正しながら精度を高められます。
人材アセスメントから得たエビデンスをもとに人材育成計画を立て、適宜修正することで、精度の高い教育を行えるでしょう。
参照記事:人材育成については以下の記事もご参照下さい
人材育成とは - 育成手法や進め方・成功のポイントを解説
3.評価に対して社員が納得しやすい
人材アセスメントは、客観的な評価であるため、信頼性が高いといえます。エビデンスにもとづいて能力や適性が数値化されるため、社員が納得しやすいでしょう。
一方で、人事評価は評価基準が一貫せず、社員から不透明な印象を抱かれる可能性があります。社員の納得感を高めるためにも、人材アセスメントの活用により、客観的な視点から多面的に評価することが大切です。
人材アセスメントの手法
社員の定着率向上や人材育成、公平な評価制度として組織に必要とされる人材アセスメントですが、具体的にはどのような手法で行われるのでしょうか。
人材アセスメントの手法は、「能力や性格、価値観」と「業務スキル」を把握する評価方法の2つに大別されています。2つのカテゴリーにもとづいて、具体的な手法を紹介します。
手法1:能力や性格、価値観を把握する評価
人材アセスメントの手法として、能力や性格、価値観を把握する評価方法があります。例えば、以下のような項目が把握されることが多いでしょう。
- 能力:論理的思考力、文章理解力、数的処理能力など
- 性格:内向性(外向性)、積極性、ストレス耐性など
- 価値観:職業に対する好み、職業観など
3つの側面から、業務や組織に対する適性を見極めます。明らかになった適性をもとに、人材配置や昇格の参考や、社員のキャリア開発に活用されます。
具体的な手法として、適性検査や職業興味検査が用いられることが多いでしょう。
適性検査
社員の採用時や管理職登用時に、能力や性格を把握するための検査です。また、部下のマネジメントの参考にしたり、社員自身のキャリア開発を目的として活用されたりすることがあります。主に論理的思考力や理解力などの能力と性格を測る項目が含まれています。
性格を把握する項目については、回答がわい曲される可能性があるため、注意が必要です。例えば、リーダーの選抜を前提として行う場合、選ばれたい思いから自分をよく見せようとする回答が目立つことがあります。すると、本来の適性を反映した結果になりにくくなるのです。
そのため、適性検査を選ぶ際には、社員の受検態度を感知できる検査を選ぶことが重要です。適性検査の信頼性にも注意することで、より精度の高い人材アセスメントができるでしょう。
職業興味検査
職業興味検査は、興味関心のある職種や心理的傾向を調べるための検査です。キャリア選択や開発を目的として、若年層の社員や自己理解を深めるために使用されます。管理職登用の際にも用いられ、適性検査と合わせて実施されるケースもあります。
ホランド理論によって作成されたVPI職業興味検査が代表的です。以下の6つの興味領域から、どのような職種に関心があるかを把握できます。
| 領域名 | 内容 |
|---|---|
| 現実的興味領域 (Realistic:R領域と略す) |
機械や物体を対象とする具体的で実際的な仕事や活動の領域 |
| 研究的興味領域 (Investigative:I領域と略す) |
研究や調査のような研究的、探索的な仕事や活動の領域 |
| 芸術的興味領域 (Artistic:A領域と略す) |
音楽、芸術、文学等を対象とするような仕事や活動の領域 |
| 社会的興味領域 (Social:S領域と略す) |
人と接したり、人に奉仕したりする仕事や活動の領域 |
| 企業的興味領域 (Enterprising:E領域と略す) |
企画・立案したり、組織の運営や経営等の仕事や活動の領域 |
能力を発揮するために、業務に対してどれだけ興味を持てるかが大切です。興味があれば、探究心や好奇心から専門性を深めるなど、自発的に研さんし成長できます。職業興味検査は、人員配置計画を考える際の参考になります。
手法2:業務スキルを把握する評価
業務を遂行するためのスキルを評価する人材アセスメントとしては、アセスメントセンターやスキルチェックなどが挙げられます。能力や適性を全般的に評価する適性検査に対し、マネジメントや専門職種など、特定の業務に必要なスキルを評価することが特徴です。
アセスメントセンター
アセスメントセンターは、シミュレーション型の演習を通して、マネジメント能力を評価する手法です。管理職や中堅社員向けの研修や昇格審査で導入されています。
具体的な演習内容の例として、部下の面談や経営上の方針を決めるディスカッション、ケーススタディなどの内容が代表的です。自社がリーダーとして求める資質をもとに、評価項目や演習内容を決定し、複数の評価者によって評価されます。
演習課題から評価するため、より実践的なスキルを把握できる点がメリットです。また、外注して実施するケースが多いですが、専門のトレーニングを受けて評価者を育成すると、自社で行うことも可能です。
スキルチェック
スキルチェックは、特定の職務の遂行能力を測るテストです。採用決定時や人材配置時に客観的に能力を評価でき、適切な人材配置に役立ちます。具体的には以下のようなスキルを評価します。
- 製造業:生産技術、機械操作
- 運転業:運転スキル
- IT系業種:ソフトウェアの基礎知識、コーディングスキル
人材アセスメントを実施する3つのステップ
人材アセスメントは、ただ実施すればよいわけではなく、目的を明確にした上で測定手法を選択し、実施することが大切です。そして、結果をもとに人材戦略や育成計画を行い、定期的に効果測定を行うことも重要でしょう。
ステップ1:目的と測定手法の明確化
目的が不明確な人材アセスメントは、社員の不信感や反発を招く可能性があります。そのような状態で実施しても、正しい結果は得られないでしょう。まずは、自社の人材面での課題をクリアにし、人材アセスメントを行う目的を明確化することが大切です。
例えば、離職率が高いという課題があれば、離職する社員の傾向を把握するために人材アセスメントを行うことが想定されます。また、管理職のマネジメント能力に偏りがある場合は、人材アセスメントを管理職登用の参考とするという活用が考えられます。
人材アセスメントを行う目的を明確にした上で、それに応じた測定方法や評価項目を選択するとよいでしょう。
ステップ2:結果の分析とフィードバック
人材アセスメントの実施後は、結果を分析し、施策に反映させていきましょう。施策に生かすだけではなく、社員本人へのフィードバックもあわせて行います。
フィードバックは、結果を用紙にまとめて一方的に共有するだけでなく、面談して伝えることが大切です。結果をもとに、キャリアプランや適性を生かせる業務など、社員のキャリア開発に役立つように伝えるとよいでしょう。
ステップ3:定期的な再測定
人材アセスメントは、実施後に再測定することで教育効果を検証できます。半年ごとや1年ごとなど、定期的に行い、変化をモニタリングすることが大切です。能力がどこまで向上しているかを把握し、施策に反映させていきます。
人材アセスメント実施の注意点
客観的な根拠にもとづいて人材戦略を立てられる人材アセスメントですが、実施にはいくつか注意するポイントがあります。実施に当たっては、どのような点を注意すればよいのでしょうか。
1.アセスメント結果だけで評価しない
人材アセスメントの結果だけで人員配置や昇格、昇進を判断することは避けましょう。人材アセスメントは多面的な評価の中の一つに過ぎません。実施したアセスメントでは計測できていない側面もあることを理解し、包括的に評価することが大切です。
2.目的を社員に共有しておく
アセスメントの目的や結果の使用目的を社内で共有しておくことが大切です。目的が不明確な人材アセスメントは社員から不信感を抱かれることがあります。不信感があると、結果にもゆがみが生じてしまう可能性があるでしょう。
例えば、社員がテストの実施に疑念を抱いていると、本心を隠して回答することが考えられます。本来の適性を把握することができず、人材アセスメントの精度が低くなってしまいます。
そのため、使用目的を明確に共有し、社員の利益につながることを丁寧に説明することが大切です。
3.求める人材要件を定期的に見直す
自社が求める人材要件は、定期的に見直す方がよいでしょう。時代や組織の人員体制の変化によって、必要な人材戦略も変わっていきます。評価する人材要件が現在の状況にそぐわない場合、本当に必要とされる人材が得られない可能性があります。
そのため、定期的に人材要件を見直していくことが必要です。人材面での課題がないかを都度確認するため、現場の意見を聞いたり、社員にヒアリングを行ったりするとよいでしょう。
アセスメント研修の紹介。参加者がアセスメントの基本から応用までを習得し、実際の業務での人材評価や選考に活用するための実践的なスキルを身につけることができます。専門家による質の高いカリキュラムで、効果的なアセスメントの実施方法を学びましょう。



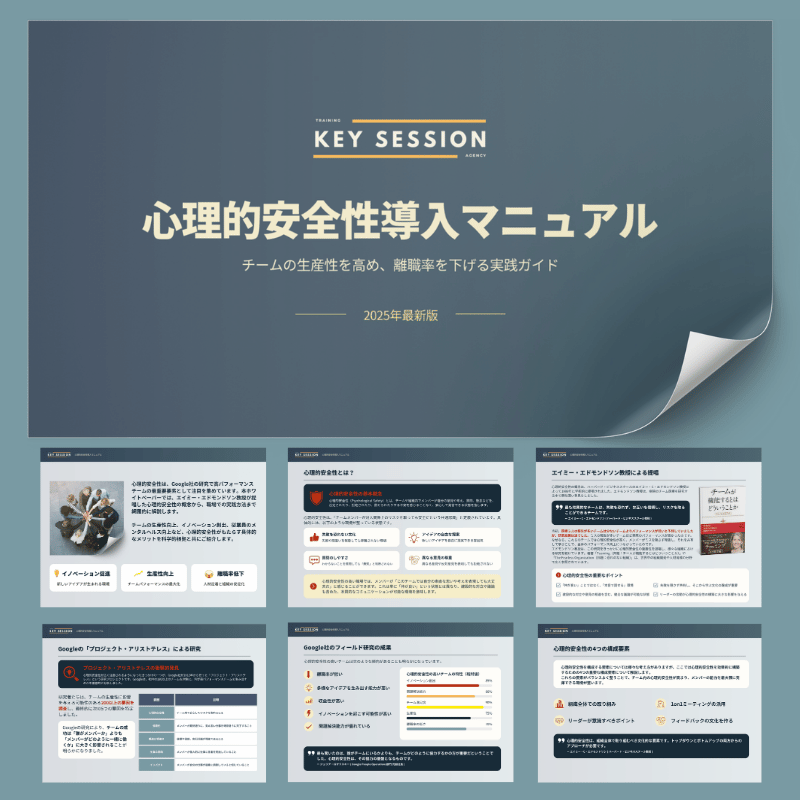


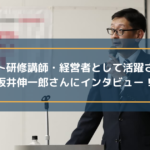

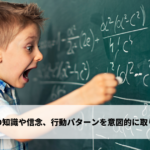
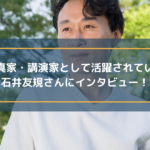
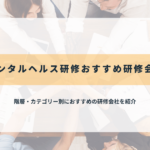





 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート