
人事評価とは、社員の業績や能力を評価し、その結果をもとに報酬や等級を決定する制度です。評価の公平性を担保し、社員の成長を促進するための重要な仕組みとして、多くの企業で採用されています。
本記事では、評価制度の「評価」「等級」「報酬」という3つの制度を中心に、具体的な評価方法や基準、導入の流れ、運用に伴う課題について詳述します。
目次
人事評価とは?
人事評価とは、社員の業績や成果、能力を一定期間において評価し、その結果にもとづいて報酬や等級などを決定する仕組みです。企業が社員に対して求める能力や役割を明確にし、その基準に沿って公平に評価するための制度といえます。
人事評価を構成する「評価」「等級」「報酬」という3つの制度や、人事考課との違いについて、より詳しく解説します。
3つの評価制度
人事評価は、「評価」「等級」「報酬」の3つの制度から構成されています。3つの制度は互いに関連しており、バランスよく機能することが理想です。
評価制度
社員の評価基準を明確にする制度です。評価項目にもとづいて一定期間の仕事ぶりをチェックし、その結果に応じて報酬や等級がどのように変化するかを定めています。
等級制度
社員の業務レベルと序列を定めるための制度です。社員を能力や職務、役割をもとに序列化し、業務遂行に関わる裁量や責任、必要なスキルを定めるものです。評価制度をもとに等級が決定され、等級を基準として給与や賞与が決まります。
報酬制度
社員の給与金額や昇給の仕組みなど、報酬について明示するための制度です。報酬には、給与や賞与、福利厚生、退職金などが含まれ、どのような評価にもとづいて報酬額が決定されるかについて定めます。
人事考課との違い
人事評価と類似した言葉として「人事考課」があります。人事考課とは、社員の業績や能力を評価し、報酬や昇給、昇進などの処遇決定を主な目的とした制度です。一方で、人事評価は処遇決定だけでなく、評価から社員の適性や能力の把握やキャリア形成を行うことも含みます。
人事考課は処遇決定を主な目的とするのに対し、人事評価は人材育成までも含む、より包括的な人材マネジメント施策であるといえます。
人事評価のメリット
人事評価は、社員の能力や業績、組織への貢献度を公平に評価し、報酬や等級を決定するものです。人材マネジメントを効率化するために不可欠な仕組みといえますが、人事評価を行うことでどのようなメリットがあるのでしょうか。
1.社員のエンゲージメントが向上する
エンゲージメントとは、社員が仕事に対してやりがいや意味を感じながら没頭できている状態を指します。エンゲージメントが向上することで、企業への愛着が増し、定着率の低下につながります。
エンゲージメントを高めるためには、社員の仕事ぶりを正当に評価する仕組みが重要です。報酬のアップだけではなく、実行プロセスを評価することでエンゲージメントが高まりやすいでしょう。
2.コミュニケーションの機会が増える
人事評価を行うためには、部下の業務内容を詳しく把握する必要があります。そのため、部下とコミュニケーションをとる機会が増えます。コミュニケーションが活発になることで、気軽に相談しやすかったり、考え方や課題を共有しやすくなったりするでしょう。
3.社員のスキルを細かく把握できる
人事評価を行うと、社員のスキルを多面的に把握できます。業務に表れている成果や発揮されている能力を総合的に把握することで、適材適所に人員配置を行えます。また、チーム内でも、適性に応じた役割を割り振りやすくなり、生産性の向上につながるでしょう。
また、人事評価では、人材開発を目的として、潜在能力や弱点も把握することがあります。重点的に伸ばす必要のある能力が明確になるため、社員一人ひとりに合わせた育成計画が立てられます。
人事評価を効果的に運用する5つの流れ
人事評価を社内の仕組みとして効果的に運用するためには、どのような流れで導入すればよいのでしょうか。以下の5つのステップにもとづいて解説します。
- 目的を明確化する
- 評価基準・項目を決める
- 評価方法を決める
- 評価者への研修を行う
- 規則の作成と社内共有
ステップ1:目的を明確化する
人事評価制度の導入に当たっては、まずは導入目的を明確にすることが大切です。人事評価の実施によって、理念やミッション、バリューといった企業が求める状態をどのように実現できるのかを具体化しましょう。
人事評価を行う目的としては、一般的には以下の3つの点が挙げられます。自社として、どういった目的で行うのかを社内で共有しておきましょう。
- 企業ビジョンの明示
- 処遇決定の公平化
- 社員の成長促進
1.企業ビジョンの明示
人事評価は、社員を評価するためだけでなく、企業として社員に求める姿を明示する目的があります。評価項目を設計する場合、「企業としてどういった社員を高く評価するか」という点を考えていきます。
しかし、何をもって「評価される社員」とするのかは企業によって異なるでしょう。企業ビジョンをベースにして、社員に対してどういった働き方を期待するかを、人事評価項目として明文化していくことが重要です。
そのため、人事評価制度は企業が社員に求める理想像を反映したものだといえるでしょう。人事評価を導入することで、社員に対して企業ビジョンを効果的に浸透させられます。
2.処遇決定の公平化
人事評価には、評価項目を基準として社員の処遇を公平化する目的があります。公平性を担保することが、社員のモチベーションを向上させ、企業への貢献度を高めます。
また、処遇に関する根拠を明らかにできるため、社員の評価に偏りが生じにくくなるでしょう。根拠にもとづいて評価できることは、評価者の安心感にもつながります。
3.社員の成長促進
社員の処遇を決めるだけでなく、能力を把握し教育に生かすことも、人事評価の目的の一つです。
評価項目を定めることで、目指すべき目標が明確になり、具体的な行動計画を立てやすくなります。適切な行動計画を立てて実行していくことで、社員の成長を促進させられるでしょう。
ステップ2:評価基準・項目を決める
次に、人事評価の目的に沿って、自社が求める人材要件を具体化した評価基準や項目を決定します。評価の種類としては、「成果評価」「能力評価」「情意評価」の3つがあります。3つの評価をもとに項目を決めていくとよいでしょう。
1.成果評価
仕事の成果や業績を評価する項目です。数値化可能な指標をもとに評価するため、客観的な評価がしやすい評価基準だといえます。
成果評価は、役職や職種によって評価基準が異なります。営業職であれば売上高や受注率など、項目を数値化しやすいでしょう。一方で、バックオフィス部門は指標が数値化しにくいため、自社として求める成果を定義づけておく必要があります。
また、結果だけでなくプロセスを含めて評価することも有効です。フィードバック時にプロセスを振り返ることで、指導や教育に生かしやすくなります。プロセスを含めて評価されることは、社員にとっても満足感につながり、仕事のやりがいを高めるでしょう。
【項目例】
- 売上高
- 受注件数
- 予算達成率・昨年比
- 課題の達成スピード
2.能力評価
業務遂行において必要な能力がどの程度身についているかを評価する項目です。業務上必要な知識やスキルに加え、スケジュール管理や問題解決力、指導力などの全般的なスキルも含みます。
能力にはすでに発揮されている保有能力、成果につながっている発揮能力、今後引き出される可能性がある潜在能力があります。どのレベルまで人事評価によって把握し活用するのかを決めておくことが重要です。
例えば、能力開発に生かすなら潜在能力まで把握したり、実績を評価するなら発揮能力を重視したりするなど、方針を決めましょう。
【項目例】
- 業務・職種固有のスキル、専門知識
- コミュニケーション力
- 企画力
- 判断力
- リーダーシップ・指導力
- マネジメント力
3.情意評価
情意評価とは、勤務態度や仕事への姿勢を評価する項目です。「主体性」「協調性」「責任感」など組織の中で規律を守り、周囲と協調しながら働けるかという点を評価します。
情意評価は、数値化することが難しく、評価者の主観に左右されやすいため、注意が必要です。目立った一面だけを課題に評価したり、特徴がわからず中間値ばかりに評価を付けるなど、形骸化する恐れがあります。
評価者は、社員の仕事への姿勢を知るために、日頃からコミュニケーションをとり、仕事の進捗状況を把握しておく必要があります。
【項目例】
- 主体性
- 協調性
- 責任感
- 規律性
ステップ3:評価方法を決める
評価基準と項目が決定したら、次にどのような方法で評価を行うかを決めましょう。評価方法は数多くあり、一つの方法で評価したり、複数の方法を組み合わせたりするなど、自社の特徴に合わせて決定します。
従来用いられてきた方法から、新しい評価手法まで、8つの方法を紹介します。
1.MBO(目標管理制度)
MBO(目標管理制度)とは「Management by Objectives」の略称で、ドラッガーが提唱した組織マネジメントの手法です。社員が上司と相談しながら目標を設定し、達成を目指す手法で、日本の多くの企業で導入されています。
目標は企業の理念に沿ったものでありながら、社員が納得した目標を設定できるため、達成のための行動につながりやすいことが特徴です。社員と企業双方の成長につながる方法であり、広く浸透している評価方法です。
2.OKR
OKRとは、「Objectives and Key Results」の略称で、Googleも導入する目標管理方法の一つです。組織全体の包括的な目標に対し、社員が何を実行すれば全体目標の達成に寄与するかという観点で社員個別の目標を決定します。
目標設定を行う点はMBOと似ていますが、OKRは比較的高い目標設定となることが多いでしょう。一般的には60~70%の達成率が見込める目標を設定します。
MBOは社員が納得して目標設定できる方法ですが、評価を求めるあまり、確実に達成できる目標しか設定しなくなる可能性があります。OKRを併用すると、現状維持だけでなく、より高い目標を持って成長していく仕組みを構築できるのです。
ただし、OKRを人事評価に直結させると、MBOと同じ方法になってしまうので避けましょう。MBOを主な評価方法としつつ、OKRは評価の参考程度にとどめておくことが望ましいといえます。
3.多面評価(360度評価)
直属の上司や同僚などの身近な関係者だけでなく、他部署を含めた複数の関係者からの情報をもとに評価を行うことです。評価者が限定的であると、一面的な特徴から評価をしてしまう可能性があります。多面的に評価することで、公平性を担保しやすくなるでしょう。
具体的な方法としては、評価する項目を決定し、業務上関わりのある人複数に回答してもらう方法が一般的です。また、評価するだけでなく、本人にフィードバックすることで自己成長が促されます。
多面評価は、立場によって異なる評価や自己評価と他者評価のギャップを知る機会となります。一方で、評価者の選定によって、評価の正当性が変動してしまうことには注意が必要です。漏れがないよう、評価者の選定には配慮しましょう。
4.コンピテンシー評価
自社内で高い仕事レベルを発揮している人材に共通する行動特性をもとに、項目を設定して評価する方法です。
実際の行動をもとに評価できる点が大きなメリットです。「マネジメント力」という評価項目を設定しても、何を持ってマネジメント力が高いかは評価者によって異なります。コンピテンシー評価で用いられる項目としては、以下のような例が挙げられます。
- スタッフの適性に応じた役割分担を行っている
- スタッフの意向をくみ取ってチームの目標を設定している
- スタッフを励ましながら目標達成を促している
以上のように、具体的な行動レベルで項目を決めると、基準がぶれることが少なくなるでしょう。また、行動特性に関する項目は、自社で実際に活躍している人材の特徴から設定するため、妥当性の高い評価ができます。
一方で、コンピテンシー評価のモデルを作成するには、データの収集や職種別のモデル作成など、多くの工数がかかります。評価方法の策定に当たっては、専門のチームを構成し、一定の期間をかけて行う必要があるでしょう。
5.バリュー評価
企業が設定している価値観や行動規範にもどついて実行できているかを評価する方法です。情意評価の一つで、数値化しにくい社員の行動や内面を把握し、結果だけでなくプロセスを含めて評価します。
結果に至るまでの行動を評価する点は、コンピテンシー評価と似ています。しかし、バリュー評価は、企業が求めるバリューに沿った行動ができているかを評価基準とすることが特徴です。企業と社員の価値観を合わせ、強固なチームを築くための手法といえます。
6.リアルタイムフィードバック
部下に対して、上司が短期間かつ高頻度で行う評価方法です。一般的な人事評価は、半年や1年ごとに行われますが、リアルタイムフィードバックは1~2週間などの短いスパンで評価します。
評価を迅速に行うことで、記憶が新しいままフィードバックされ、効果的な成長につながります。また、頻繁に評価を行いフィードバックすることで、上司と部下のコミュニケーションも活発になりやすいでしょう。
7.ピアボーナス
ピアボーナスとは、社員同士でインセンティブを送り合う評価制度です。オンラインのチャットツールを活用し、感謝の気持ちや賞賛を伝えます。社員からの評価はポイントや社内の仮想通貨としてためられ、組織にどれだけ貢献したかを可視化できる仕組みが特徴的です。
評価者が上司ではなく、横の関係性で評価できるので、社員が納得しやすい方法といえます。ピアボーナスを既存の業績評価や能力評価に加えて導入すると、社員の納得感や公平性を高められるでしょう。
8.ノーレイティング
ノーレイティングは、ランク付けを行わない人事評価で、アメリカを中心に広がっている制度です。評価期間を定めず、社員は評価者と1on1を定期的に実施しながら評価します。評価と同時に目標へのフィードバックを行うといった教育をかねた方法といえます。
対話を重ねながら評価されるため、社員の納得感を得やすい点がメリットです。一方で、上司に人件費の権限を一任するため、評価者の負担が大きくなりがちです。導入する際には、負担軽減のため、部分的に移行していくことが望ましいでしょう。
ステップ4:評価者への研修を行う
人事評価を公平に行うには、評価者のスキル向上が必要です。制度導入に当たっては、評価者への研修を行い、正確な評価ができる人材の育成が求められます。
評価者への研修では、人事評価エラーや面談スキルについての理解を促しましょう。
1.人事評価エラーの防止
人事評価エラーとは、評価者の思い込みや心理状態によって、実態とは異なる評価を下してしまうことです。評価が不公平となり、社員の不満や不信感につながる可能性があります。生じがちな人事評価エラーを意識し、公平な評価ができる評価者を育成することが求められます。
人事評価エラーは、無意識的に発生するため、偏りが起きるパターンを理解し、生じないように意識することが大切です。評価者研修において、代表的な人事評価エラーの例と対策を伝えられるとよいでしょう。
代表的な人事評価エラー例は以下の通りです。
| エラー名 | 説明 |
|---|---|
| ハロー効果 | 「過去に大きな失敗をしているので、ミスが多いはずだ」など、一部の特徴や印象に影響されて、全体的な評価に偏りが生じること。 |
| 中心化傾向 | 5段階評価で3と評価するなど、極端な評価を避けて、当たり障りのない評価をしてしまう傾向。被評価者のことをよく知らない場合に生じやすい。 |
| 寛大化傾向 | 実際よりも甘い評価をつけてしまうこと。「嫌われたくない」「頑張っている部下を評価したい」という動機で生じることが多い。 |
| 厳格化傾向 | 実際よりも厳しい評価をつけてしまうこと。優秀な評価者が自分自身を基準にして、被評価者を低く評価することにより生じやすい。 |
| 論理的誤差 | 「プレゼンテーションがわかりやすいので、コミュニケーション能力も高いだろう」と被評価者の業績や行動をよく観察せずに、評価者の論理で評価してしまうこと。 |
| 対比誤差 | 「自分なら、この仕事は3時間で終わらせられる」「顧客に対してもっと丁寧に対応する」など、評価者自身との比較で評価してしまうこと。 |
| 近接誤差 | 「先月大きな案件を受注したから」という理由でよい評価を付けるなど、直近の出来事から評価してしまう。対象期間の初めの出来事が無視される。 |
| アンカリング | 被評価者の第一印象や自己評価の点数など、始めに与えられた情報をもとに評価してしまうこと。 |
| 逆算化傾向 | 評価する対象者の順位を決めてから、総合点を調整すること。「○○さんは昇格後最初の評価だから、一番低くても文句は出ないだろう」と考えて評価を低くするなど、意図的な評価エラー。 |
2.面談スキルの向上
評価面談やフィードバックに関して、評価者の面談スキルの向上も必要です。評価面談により、詳しく能力を把握することで、多面的な評価が可能となり、社員が抱える現状の課題も明らかになります。
また、明らかになった課題から、部下の能力やキャリアビジョンに合わせて目標設定を行うことも大切です。目標をもとに、具体的な行動を促していくと、人事評価を最大限に活用できます。
以上のように、人事評価において面談スキルは評価だけでなく、人材育成の面からも必要な要素だといえるでしょう。評価者である管理職には、目標設定やコーチングなどの動機付けを高めるマネジメントスキルが求められます。
ステップ5:規則の作成と社内共有
評価項目や方法が決まり、評価者の研修体制が整ったら、人事評価に関する社内規則を作成し、文書化しましょう。規則の作成は法的な義務ではありませんが、作成しておくと運用がスムーズになります。
また、導入時には人事評価に関する説明会を開催し、社内への共有を図りましょう。
参照記事:人事評価面談については以下の記事もご参照下さい。
人事評価面談とは - 目的と効果的な面談を実施するためのポイントを解説
人事評価に生じがちな課題
人事評価は、人材マネジメントの観点から不可欠な制度といえます。しかし、導入し効果的に運用するためには、さまざまな課題が生じます。
1.運用に伴う労力が大きい
人事評価を導入するには、運用に伴う工数が生じます。評価基準の明確化や項目の策定と見直し、社内への周知など、人事担当者には多大な労力を必要とします。
また、評価を行う管理職も、評価対象となる部下の行動や成果を記録し、定期的に評価を行わなければなりません。また、人事評価の結果を丁寧にフィードバックする面談も求められます。そのため、通常業務と平行して負担が増大するでしょう。
人事評価制度を丁寧に実施しようとするほど手間がかかるため、実施者の不満や反感を買ってしまう可能性があります。また、リソース不足から制度が定着しなかったり、形骸化したりする恐れもあるでしょう。
評価制度をどこまで細かく設定するか、社員の手間と効果のバランスを考慮しながら考える必要があります。
2.評価基準が一貫していない
評価基準が一貫せず、人事評価の公平性を担保しにくいことも生じやすい課題の一つです。売上高や受注件数など、数値化できる項目なら不公平感が生まれにくいですが、数値だけでは測れない項目もあります。
特に、積極性を「O・△・×」の3段階で評価するような、絶対的基準がない評価項目は、評価者の主観による偏りが生じがちです。人事評価エラーを防止するための教育機会を設け、客観的な視点で評価できるように促すことが大切でしょう。
また、評価者同士で基準を合わせる機会を設けることも有効です。例えば、評価を行う管理職が集まり、どういった基準や行動をもとに評価しているかを話し合う会議を行うとよいでしょう。
3.制度の運用自体が目的化してしまう
企業ビジョンの達成などの本来の目的ではなく、人事評価を行うこと自体が目的化してしまうという課題も生じやすいでしょう。評価プロセスに関与する社員のリソース不足や評価方法の理解不足から「項目に沿って評価しているだけ」というような状態です。
形骸化しないためにも、評価に携わる社員が人事評価について正しく理解することが重要です。また、特定の社員に人事評価の負担が集中しないような仕組みづくりも求められます。
人事評価の方法について周知したり、評価の効率化を進めたりするなど、スムーズに機能するよう取り組んでいくことが大切です。
評価者研修は評価者としての基本スキルを学び、人材育成のツールとして評価制度を活用するための研修です。 正しい管理プロセスを学ぶことで、目標の設定から成果の評価までを効果的に行います。




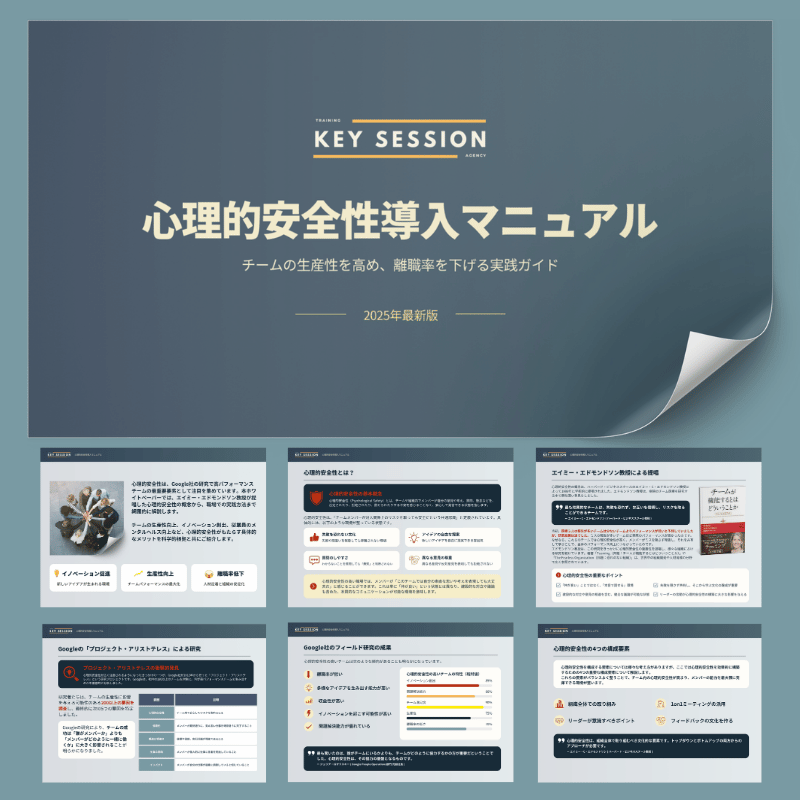







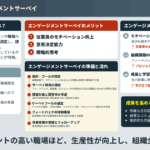
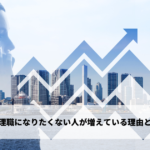


 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート