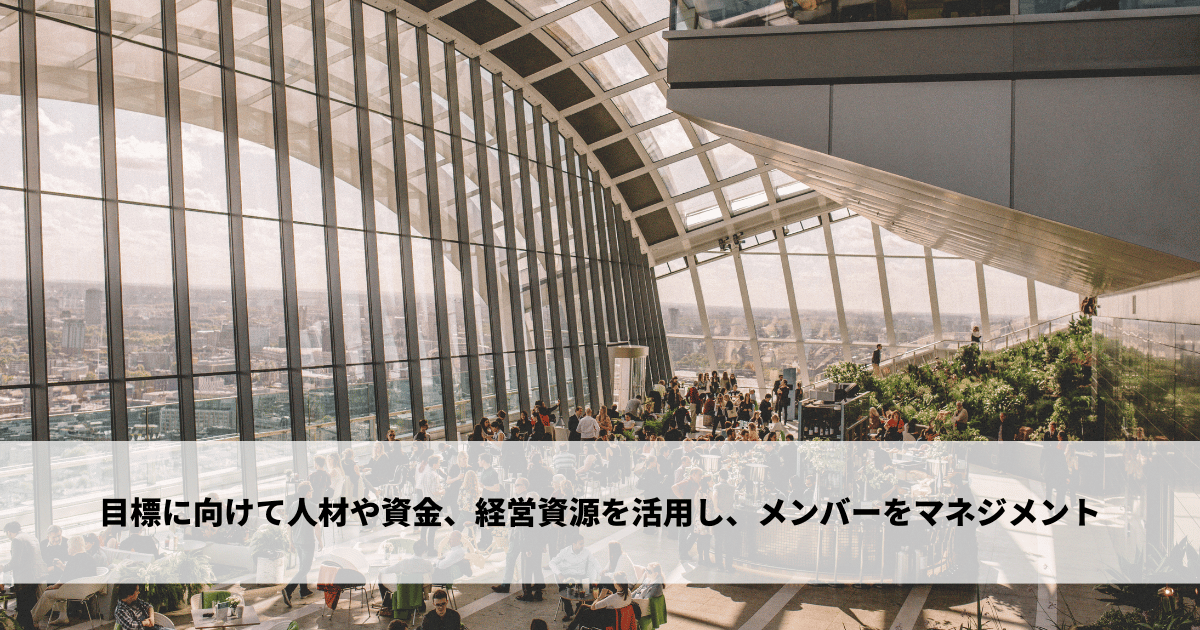
組織運営において管理職に求められるスキルとはどのようなものでしょうか?また、そのスキルを高めるためにはどのような研修が有効なのでしょうか?
本記事では、管理職に必要とされる5つのスキルに焦点を当て、それぞれの重要性と具体的な研修例を紹介します。
まず、マッキンゼーの7Sモデルを活用し、戦略や組織構造、システムなどのハード面、そしてスキルや人材、経営スタイル、共有価値観といったソフト面に分けて組織を効果的に運営するための基盤を築きます。その上で、目標設定スキル、進捗管理スキル、柔軟なコミュニケーションスキル、モチベーション管理スキル、リスクマネジメントスキルの5つを強化するための具体的な研修内容について解説します。
信頼される管理職を育成し、組織全体の運営能力を向上させるための実践的な方法ご紹介します。
目次
組織運営とは?
組織運営とは、企業の目標達成に向けて人材や資金、情報などの経営資源を活用し、メンバーをマネジメントすることです。組織のリーダーは、メンバーが能力を発揮し、成長を促せるようコミュニケーションをとる姿勢が求められます。
そして、組織が円滑に機能するよう、業務体制や人員を適切に調整し、目標達成を推進する取組を実行していく必要があります。
組織運営の7つの要素「マッキンゼーの7S」
組織運営に重要な要素として、「マッキンゼーの7S」というフレームワークが有名です。7つの要素から、組織の構造や体制、ビジョンなどを検討し、効果的な組織変革に役立てます。「マッキンゼーの7S」をもとに、組織運営に必要な要素について解説します。
関連記事:マッキンゼー 7S フレームワークの解説
ハード面の3S
マッキンゼーの7Sでは、7つの要素をハード面とソフト面に分類しています。ハード面は以下のように、組織全体の枠組みに関連する要素であり、制度を変更すれば比較的変えやすい側面といえます。視点例をもとにして組織を分析すると、効率的な運営に役立つでしょう。
| 要素 | 説明 | 視点例 |
|---|---|---|
| Strategy(戦略) | 目標達成の方向性 | 自社の強みと弱み 競合他社と比較した自社の位置づけ |
| Structure(組織構造) | 階層や部門の構成 | 上司と部下の関係 経営層と一般社員との関係 リーダーシップや責任の所在 |
| System(システム) | 制度やシステム、ルール | 機能していない評価制度はないか パフォーマンス低下につながるシステムはあるか |
Strategy(戦略)
Strategy(戦略)は、目標達成のための企業がもつ方向性を指します。目標達成のためのアプローチは一つではなく、自社の強みや弱み、競合他社との関係を考慮した戦略立案が必要です。そして、戦略をもとに、サービスや商品展開、開発、営業手法などの具体的な戦略を計画します。
組織の中核的な行動指針ともいえるもので、戦略が決まっていないと他の要素が一貫性をもちにくくなるでしょう。戦略を明確化し、社員への浸透を目指すことが重要です。
KeySessionでは貴社の理念浸透研修導入をお手伝いをいたします。
Structure(組織構造)
Structure(組織構造)とは、階層や部門の構成など、組織の仕組みを指します。組織構造によって、職務の権限や指揮系統が異なります。例えば、経営層の権限が強いトップダウン型と、現場に権限を与えるボトムアップ型では組織のあり方が違うでしょう。
どのような組織構造が、自社のビジョンを果たすのに最適かを考えるために役立つ要素だといえます。
System(システム)
社員の力を発揮するためのルールやシステムを指します。例えば、人事評価制度、就業規則、会計制度などの規則や目標管理方法や情報共有フローなどの業務プロセスが含まれます。
システムが確立されていると、社員の日常業務をサポートしたり、働くためのモチベーションとなったりする面で役立つでしょう。
ソフト面の4S
ソフト面の4Sは、ハード面に比べて、スキルや人材、共通の価値観といった形がはっきりしていない要素です。そのため、変化には時間がかかるとされています。
| 要素 | 説明 | 視点例 |
|---|---|---|
| Skill(スキル) | 所有する技術や知識 | 競合他社と比較して優れているノウハウ 組織に不足しているスキル |
| Staff(人材) | 社員の情報 | どのような人材がいるか 適切な人材配置や採用、教育は行われているか |
| Style(経営スタイル) | 企業理念やミッション | 経営層と社員のビジョン理解のズレはないか 管理職だけでなく社員まで浸透しているか |
| Shared value (共通の価値観) | 社風や雰囲気 | 経営陣のリーダーシップの程度 意思決定はトップダウンかボトムアップか |
Skill(スキル)
企業が所有する技術や知識を指す要素です。社員個人のスキルだけでなく、技術力、開発力、販売力など、企業全体が有するスキルも含みます。目標達成のためには自社が保有するスキルと不足しているスキルを分析した上での施策実行が重要です。
Staff(人材)
自社にどのような社員がいるかという情報を指します。経歴や実績などの表面的な部分だけではなく、本質的な特性を把握するとよいでしょう。例えば、保有スキルや仕事への意欲や適性、理念に沿った態度ができているかなどの点です。
自社に適切な人材が足りているか、基準を満たす人材を採用できているかといった点を考慮するために必要な要素です。
Style(経営スタイル)
企業理念のことで、7Sの中で最も重要とされています。経営陣から社員まで同じ方向を向いて事業活動を行うためには、理念の浸透と実行が欠かせません。メンバーが一丸となって進んでいける組織を目指すため、社員に理念浸透がされているかのチェックが必要です。
参照記事:理念浸透については以下の記事もご参照ください
理念浸透とは - 重要性と理念浸透の成功のポイント
Shared value (共通の価値観)
企業の社風や雰囲気を指します。就業規則などの社内規定に明記されている内容だけでなく、暗黙の了解として組織を形成している雰囲気も含みます。明文化されない風土を言語化し、メンバー間で共有できると、組織のあり方を考えるきっかけになるでしょう。
組織運営に求められる管理職の姿勢
効果的な組織運営に求められるのは、部下から信頼される管理職です。信頼される管理職を登用できるように人材要件を見直したり、育成計画に反映させたりすると、組織としての力が向上するしょう。部下から信頼感を得るために必要な管理職の姿勢について解説します。
1.部下の意見を率直に受け止める
部下の信頼感を高めるためには、意見を頭ごなしに否定するのではなく、一旦受け止める姿勢が大切です。意見を十分に聞いた上で、違うと感じる点は意見を述べ、学べる部分は素直に吸収する態度が信頼を形成します。
部下にとっては、「しっかり意見を聞いてもらえる」という安心感が生まれ、意見交換が活発になります。また、部下は自分の考えを積極的に発信するようになり、新しい発想が生まれやすくなるでしょう。
2.情報を隠さずオープンにする
組織運営において、「透明性」を重視することは社員の信頼につながります。透明性とは、隠したりごまかしたりせずにオープンに話す態度です。
例えば、目標設定や業務の目的などを共有するとき、具体的な情報を省略して伝えてしまう場合があります。管理職の意図や背景などの具体的な情報まで伝えると、「正直に話してくれている」と、信頼感の構築につながります。
3.裁量範囲を増やしサポートに徹する
部下の業務の裁量範囲を増やすことで、仕事を任せてもらえているという信頼感につながります。そのため、一人で業務を抱え込まず、部下に仕事を任せて自分はサポートに徹するという態度をとれるとよいでしょう。
部下の目標達成を優先してサポートに徹する態度は、「サーバントリーダーシップ」として近年注目されています。上司が部下が目指すべき方向性や目標を示し、傾聴や励ましなどのサポートを通じて達成を支援するリーダーシップスタイルです。
社員が力を発揮できるよう管理職が支援すると、社員のエンゲージメントが高まり、強固な組織が形成できるでしょう。
▼ 組織拡大時の管理課題については以下の記事もご参照ください
100人の壁とは?組織拡大の壁を乗り越える方法や研修例を紹介
組織運営に必要な管理職のスキル
企業に存在する各組織を効率的に運営できるかどうかは、管理職のスキルに影響されます。どのようなスキルをもった管理職を育成すればよいか、必要な5つのスキルから解説します。
1.目標設定スキル
管理職には、社員や組織の目標を適切に設定するスキルが求められます。目標を設定し、その達成を意識できると業務に対するモチベーションが高まり、生産性が高い状態で業務を遂行できるでしょう。
しかし、目標設定が適切でないと、モチベーションが低下してしまう場合があります。例えば、明らかに達成不可能なノルマや現場の意見を反映していない目標は、社員の納得を得にくいでしょう。
納得感のない目標は、「させられている」という感覚に陥り、モチベーションが低下してしまいます。目標として適切なのは、「頑張れば達成できる目標」や「現場の意見を考慮した目標」です。
そのため、管理職には、経営層から求められる目標と、現場の工数や人材のスキルとの兼ね合いを調整する力が求められます。社員が納得できるような目標設定ができるマネジメントスキルが必要なのです。
2.進捗管理スキル
目標に沿った業務やプロジェクトを計画通り実行できる能力も管理職には必要です。適切な目標を立てられたとしても、その実行をマネジメントする能力がないと意味がありません。
業務フローの計画や適性を見極めた人を動かす仕組みづくりなど、プロジェクト管理を行う力が求められます。そのために、行程ごとに納期設定し進捗確認を都度行うなど、こまめなチェックが必要です。
また、予算にかなった計画を実行するなど、費用面への配慮も求められます。総合的な視点からプロジェクト管理を行う、冷静な対応力が必要といえるでしょう。
3.柔軟なコミュニケーションスキル
管理職として、部下だけでなく上層部ともやり取りができる、柔軟なコミュニケーションも求められます。
部下に対しては、日頃からコミュニケーションをとり、現場の課題や現状を詳しく理解した上で、課題を解決する対応力が必要です。また、経営層の意向を部下にわかりやすく伝え、社内の方針を浸透させていく関わりも求められます。
また、経営層との折衝においては、現場の実情を踏まえた業務や目標の調整を行います。経営層との間に立って、互いの意向を理解しながら調整する、高度なコミュニケーション能力が必要といえるでしょう。
4.モチベーション管理スキル
部下のモチベーションを管理する力も求められます。モチベーションが下がり、成果が上がっていない部下に関与し、目標を達成できるように関わります。
モチベーション管理には、部下の特性を見極めた対応が欠かせません。例えば、解決策を提示された方がよいのか、自分で思考し答えを出せる方がよいのか、動機づけの方法は一人ひとり異なります。部下の特性を把握し、柔軟に対応できる能力が必要です。
また、モチベーションが低下している部下がいたとしても、成果を出せる仕組みづくりも求められます。部下の役割を見直して適性のある業務を割り振ったり、他の部下がカバーできるようにしたりするなど、業務の調整力も求められます。
5.リスクマネジメントスキル
想定外のトラブルが生じたときに対応できるよう、リスクマネジメントを行う能力も求められます。管理職は、現場で生じた事故やクレームに対しては、主体となって対応する役割が求められます。管理職がリスクマネジメントへの意識が薄いと、企業の信用を失いかねません。
そのため、管理職にはリスクへの対応やその防止策を十全にできるスキルが求められます。具体的には、業務上で想定されるリスクを把握し、対応方法や体制の整備と部下への共有を行う対応力が必要です。
また、トラブル発生時に、管理職が自ら解決に当たるスキルも欠かせません。管理職登用前にトラブル対応の実務経験が積めるよう、キャリアフローを考慮するとよいでしょう。
参照記事:管理職に求められる役割とその重要性については以下の記事もご参照下さい。
管理職とはどこから?含まれる役職と管理監督者との違い、役割を解説
組織運営を効果的にするための管理職研修例
組織運営を行える管理職を育成するには、研修を実施し、必要なマインドや能力を身につける必要があります。具体的には、どのような研修を行えばよいのでしょうか。3つのテーマ例を紹介します。
リーダーシップの理解
組織のリーダーとしての役割を果たすには、リーダーシップに関して正しい理解を深める研修が必要です。組織に求められるリーダーの形を理解し、適切に部下を管理、育成できる管理職を育てます。
【具体的なテーマ例】
- リーダーシップの類型
- リーダーに求められる役割
- 部下から信頼されるリーダーの条件
- 状況に応じたリーダーシップの発揮
- 論理的に伝えるためのコミュニケーション方法
実務スキルの向上
管理職としての実務スキルの向上を目的とした研修も重要です。部下への業務の割り当て方や権利委譲、サポート方法など、業務が円滑に進む仕組みづくりを実際のワークを通じて行うとよいでしょう。
【具体的なテーマ例】
- 仕事の任せ方
- 権利委譲のやり方
- プロジェクト管理方法
- インバスケット演習(課題を用いたワーク形式)
コミュニケーション力の強化
部下と適切に関わるためには、コミュニケーション力が欠かせません。リーダーシップのように部下を導くような関わりだけでなく、サポーティブに関わる力も必要です。
具体的には、部下の意見や考えを引き出すためのコーチングスキルや、相手を傷つけずに主張するアサーションなどが挙げられます。ハラスメント対策など、部下との距離を保った関わりを促進するテーマも必要でしょう。
【具体的なテーマ例】
- コーチングスキル
- アサーション
- ハラスメント対策
管理職育成についてはこちらの記事もご参照ください。
【5ステップで解説】企業に求められる新任管理職育成のポイントは?
管理職向け研修の導入をサポートします
最適な管理職向け研修の選定は、KeySessionにお任せください。
専門的な知識と経験を持つ我々が、貴社のニーズに合わせた最良の人材育成・研修会社をご提案します。
優秀な人材が管理職への転向をスムーズに行えるように、そして管理職としての任務を存分に果たしてもらえるようにサポートするのも企業の大切な役割です。管理職が安心して働けるように必要な管理職向け研修の内容について紹介します。





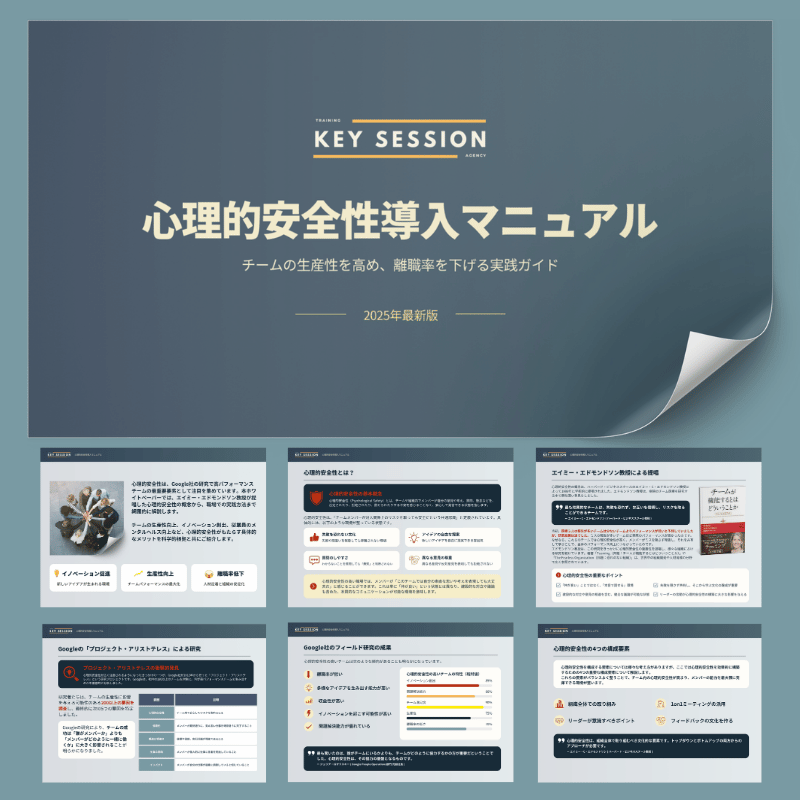





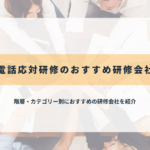

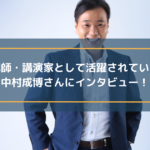





 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート