
| 研修プラン | 研修時間 | 研修会社 |
|---|---|---|
| 150分 | ||
| 90~180分 | ||
| 3時間/6時間 | ||
| 4時間 | ||
| 90~180分 | ||
| 120~180分 | ||
| 4時間 | ||
| 3時間 | ||
| 4時間 | ||
| 6時間 |
「ハラスメント研修では、どのでような内容を学べるかわからない」「ハラスメント研修を実施することで、どのような効果があるの?」
このような疑問や悩みを抱えている経営者や責任者も多いのではないでしょうか。
当記事では、ハラスメント研修の内容や目的、カリキュラム例、おすすめのハラスメント研修について紹介していきます。ハラスメント研修を検討している担当者の方は、ぜひご一読ください。
この記事でわかること
- ハラスメント研修の目的
- ハラスメント研修のカリキュラム例
- おすすめのハラスメント研修
センシティブなテーマであるハラスメント研修を実施して効果を出すためには、研修内容や講師の質が重要です。とはいえ数多くの研修会社から自社に適した研修を選ぶのは困難なのではないでしょうか。
キーセッションでは、複数の研修会社の中から貴社のご要望に沿ったハラスメント研修のご案内が可能です。相談は無料なので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
目次
ハラスメント研修とは

ハラスメント研修とは、会社内でハラスメントが発生しない環境を整えるため、一人ひとりの意識を高める研修です。
ハラスメントには、パワハラやセクハラ、マタハラ、モラハラなどさまざまな種類があります。上司はハラスメントをしているつもりがなくても、受け手の感じ方次第ではハラスメントです。
ハラスメント研修では、ハラスメントに該当する状況や種類、気をつけるポイントなどを学びます。
ハラスメント研修の目的・効果
ハラスメント研修の目的・効果は、以下の3点です。
- ハラスメントの防止
- 社員のリテラシー強化
- 職場コミュニケーションの改善
それぞれを詳しく見ていきます。
ハラスメントの防止
ハラスメント研修の実施の最大の目的は、社内におけるハラスメントの発生を防止することです。
研修では、ハラスメントの意味や、どんな行為がハラスメントにあたるのかという基礎的な内容を学びます。それらを全員が学び、認識を共有することで、ハラスメント行為の防止につながるのです。
ハラスメントは、上司や管理職のハラスメントに対する意識不足で生じることもあります。研修を通して、パワハラやセクハラにあたる行為はなにかを理解することで、すでに生じているハラスメントを抑制したり、未然に防ぐ効果が期待できます。
社員のリテラシー強化
ハラスメント研修を実施することで、社員のリテラシーが強化される効果も期待できます。
ハラスメントは、リテラシーがなく価値観の違いを理解できていないことが原因のケースも多いです。叱咤激励のつもりでも、年代によってはハラスメントと捉えるケースもあります。
価値観の違いを学んだり、ハラスメントへの理解を深めたりして、社員のリテラシーを強化します。
職場コミュニケーションの改善
職場のコミュニケーションを改善するのも、目的の一つです。
上司と部下のコミュニケーション不足が、ハラスメントにつながることもあります。普段からコミュニケーションがとれていないため、上司の意図と部下の捉え方に違いが生じてしまうのです。
また、ハラスメントを避けたいあまり、上司と部下がコミュニケーション不足になるケースもあります。正しいコミュニケーションのとり方を学び、人間関係を改善させる効果も期待できます。
ハラスメント研修の重要性
ハラスメント研修の重要性は、年々高まっています。2020年の労働施策総合推進法改正により、ハラスメントを防止するための取り組みが義務化されました。
ハラスメントを防止するための取り組みには、社内窓口を設置したり、匿名でアンケートを実施したりする方法などがあります。そして、ハラスメント研修の実施も重要な取り組みの一つです。
社員のハラスメントに対する認識を統一して、意識を高めるためには、研修の実施が効果的です。そのため、ハラスメント研修を導入する企業は増えています。
ハラスメント研修の内容
ハラスメント研修の内容は、以下の通りです。
- ハラスメントの基礎知識
- 具体例
- よい職場環境の作り方
- 対処法
ハラスメントは数多くの種類があり、すべて把握するのは難しいです。そのため、パワハラやセクハラの防止に焦点を当てた内容をメインに学びます。
ハラスメントの基礎知識や具体例についてわかっていても、行動しなければ意味がありません。ハラスメントの具体例を学ぶことで、行動への移し方も身につけます。
参考:厚生労働省『職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)』
参考:厚生労働省『「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」』
ハラスメント研修の対象者
ハラスメント研修の対象は、社員全員です。
管理職や上司は部下と接する役職のため、ハラスメント研修の受講が欠かせません。
新入社員であれば、自身がハラスメントを受けた際の対処法を習得可能です。対処法を知っておくことで、いざハラスメントを受けた際に適切な行動がとれます。
また、役職や立場に合わせて、研修を複数回実施するのもおすすめです。管理職や上司だけの研修と、部下と一緒に受ける研修の両方を実施しましょう。
ハラスメント研修のカリキュラム一例
ハラスメント研修のカリキュラム例は、以下の通りです。
※1日での研修を想定しています。
| 内容 | 目的 | 手法 |
|---|---|---|
| ハラスメントとは ・ハラスメントの定義 ・ハラスメントの種類 |
ハラスメントについての知識を深め、参加者全員で共通認識を作る | 講義 |
| ハラスメント防止取り組みの必要性 ・ハラスメント防止強化の背景 ・ハラスメントが企業に与える影響 ・ハラスメントが人に与える影響 |
・ハラスメント防止の取り組みが必要であることを理解する ・ハラスメントを自分事として捉える視点を持つ |
講義 |
| ハラスメントセルフチェック | ・自分の言動を振り返る ・職場全体のハラスメントに対する認識を確認する |
個人ワーク |
| パワーハラスメントについて ・パワーハラスメントとは ・パワーハラスメント防止法について ・6つのタイプ ・パワーハラスメントの原因 |
・パワーハラスメントについての知識を深める ・誰もが当事者になり得ることを自覚する |
講義 個人ワーク グループワーク |
| セクシャルハラスメントについて ・セクシャルハラスメントとは ・2つの種類 ・セクシャルハラスメントの原因 |
・セクシャルハラスメントについての知識を深める ・誰もが当事者になり得ることを自覚する |
講義 個人ワーク グループワーク |
| ハラスメント対策方法 ・社内コミュニケーションについて ・ハラスメントをしてしまったら ・ハラスメントを受けたら ・ハラスメントを目撃したら |
・コミュニケーションの基本を見直し実践につなげる ・ハラスメントを放置しない心構えを作る |
グループワーク |
| ハラスメント事例検討 | 個人として、職場としての取り組みや意見を整理し、行動を考えるきっかけを作る | グループワーク |
| 振り返り | 研修内容を振り返り、明日からできることを考え実践につなげる | 個人ワーク |
⇒【2023年】職場で起こりえるハラスメントの種類と対策方法
おすすめのハラスメント研修
おすすめのハラスメント研修は、以下の5つです。
- ハラスメント防止研修「サミット人材開発株式会社」
- 【企業向け】階層別ハラスメント研修「合同会社JEIT」
- 具体的で現実的な”実践で活きる”内容を学べるハラスメント研修「株式会社ノビテク」
- 多様化するハラスメントを学ぶハラスメント研修
- ハラスメント防止研修【実践型】働きがいのある職場環境作りで社員のモチベーションを高める
それぞれの研修について紹介します。
ハラスメント防止研修「サミット人材開発株式会社」
サミット人材開発株式会社が提供するハラスメント研修は、組織の倫理観とコンプライアンス意識を高め、パワハラ境界線を理解しながら適切な指導法を習得することを目指す研修です。
同社は豊富な実績と専門知識を誇り、若手社員との円滑なコミュニケーションや相談対応力の強化など、現場で役立つ具体的手法を提供します。
本研修では、21世紀のコンプライアンス要請に応え、パワハラ予防策や部下への傾聴・受容スキルを獲得。さらに、多様化するモチベーションに応える柔軟な指導スタイルを学ぶことで、組織全体の信頼性と生産性向上が期待できます。講師による対話式講義で、理論と実践を結びつけ、実務に直結したスキルを身につけることが可能です。
同社は長年培った知見と現場密着型の指導方法に定評があり、多様な業種・職場環境への対応力を誇ります。実際の事例や対話を通じて、具体的な改善指針を得ることができる点も特徴です。サミット人材開発のハラスメント防止研修は、未来志向の職場文化を築く上で欠かせないプログラムといえます。信頼されるリーダー育成への一歩を踏み出す機会となるでしょう。
【企業向け】階層別ハラスメント研修「合同会社JEIT」
職場におけるハラスメント防止は、組織の健全な成長と人材定着に欠かせません。「階層別ハラスメント研修」を提供する合同会社JEITは、日本ハラスメントリスク管理協会認定講師を擁し、法的根拠と現場感覚を融合した独自のプログラムで多様な役職層にアプローチします。
同社の研修では、過剰な言葉狩りに陥らず、尊重と理解を基盤に、実践的なワークや事例研究を通じて問題解決力を養成。例えばパワハラ防止法に基づく境界線明確化、叱り方のクセを知り改善へ導く指導法確立、相互支援の風土づくりなど、実務に即した学びを提供します。
研修後のフォローアップ体制も万全で、受講者の成長を継続的にサポート。教育現場で成果を上げた講師陣が、管理職から一般社員まで共に学び、安心・安全な職場文化を育むことで、生産性とモチベーションを高めます。
同社は学校法人や企業向けに多彩な実績を重ね、現場で培ったノウハウを活かして改善策を提示。さらに個別相談や進捗確認を行い、参加者が自信を持って行動できるよう支援します。講師陣は元校長やトップ校で成果を挙げた教育者、企業経営者など多彩な経歴を持ち、理論と実践を兼ね備えています。受講後も連携を継続し、組織全体での改善を後押しします。こうして誰もが尊重される環境が生まれます
【企業向け】階層別ハラスメント研修 (90~180分)
パワハラ防止法の理解から実践ワークまで、管理職が適切な指導力を身につけ安心・安全で成長促進する職場環境を構築し、生産性と定着率を向上させる企業向け階層別ハラスメント研修。マタハラ・パタハラ対策や叱り方ワークを交え、メンタル不調者減少と人材定着をサポートします。
具体的で現実的な”実践で活きる”内容を学べるハラスメント研修「株式会社ノビテク」
実際に起こったハラスメント事件を用いて原因や対策を検証し、具体的で現実的な実践で活きる内容を学べる研修です。ハラスメント傾向自己診断チェックを実施するため、他人事ではなく自分事として受講できます。
また、講師はさまざまなジャンルの方々と連携しているのも特徴です。そのため、会社に適した講師を紹介してもらえます。講義形式やセミナー形式、オンライン形式などさまざまな受講方法があるため、スケジュールにも合わせやすいです。
実施期間は3日と、短期間で受講できます。できるだけ短い期間で、ハラスメント研修を実施したい場合におすすめです。
セクハラ・パワハラ防止研修 (3時間)
セクハラ・パワハラ防止の基礎から実践まで、事例やワークを通じて管理職が安心できる職場環境づくりのポイントを学べます。
多様化するハラスメントを学ぶハラスメント研修「株式会社モチベーション&コミュニケーション」
本研修ではこの2大ハラスメントが発生するメカニズムから、コミュニケーションの取り方まで、実例を交えながら学んでいきます。
また「自分はハラスメントをしていない」と思い込んでいる場合もあります。問題行動のシチュエーションをケーススタディに用いるなどして、自身の行動が問題行動であったか気づきの促進が可能です。
さらにリモートハラスメントなど、多様化するハラスメントにも対応し、今まさに必要なハラスメントの知識、対応方法を習得することができます。
株式会社モチベーション&コミュニケーションは、社名の通り、組織のコミュニケーション課題の解決に特化した研修を得意としています。豊富な研修実績で、その業種に合った研修内容を作成するため、受講後すぐ実務で活かせるのも特徴です。
実施期間は1日4時間のため、短時間でハラスメントについて学べます。そのため、通常業務が忙しく、数日間の日程が抑えられない場合におすすめです。
多様化するハラスメントを学ぶハラスメント研修 (4時間)
実例を交えたセクハラ・パワハラの境界線とNG行動を明確化し、適切な指導法からリモート含む相談・苦情対応まで総合的に習得。部下・異性社員とのコミュニケーションスキル向上で風通しの良い職場づくりを実現。管理職が主体的に予防策を実践し、離職率低減と組織活性化を図ります。
ハラスメント防止研修【実践型】働きがいのある職場環境作りで社員のモチベーションを高める「株式会社PDCAの学校」
株式会社PDCAの学校が主催するハラスメント防止研修は、役員や経営幹部、管理職を対象とした研修です。
研修では、セクシャルハラスメントや妊娠出産等に関するハラスメントなど、ハラスメントの基礎知識を学ぶとともに、ハラスメントの防止への意識を向上させます。日頃のコミュニケーションで、なにか問題は無いか見直していきます。
2022年4月1日より、中小企業にも改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が義務化されたため、中小企業も社員教育や相談体制の整備などが必要です。研修では、中小企業ではどのような対策をすればよいのかを学べます。
また、1社1名から参加可能な研修を主催しています。実践トレーニングを通して受講者を育成し、習慣化できる仕組みを提供することで、職場に戻ってからも受講者が自分でPDCAを回しながら成長できる研修です。
実施期間は4時間と短いため、スケジュールを気にせず実施できます。
ハラスメント防止研修【実践型】働きがいのある職場環境作りで社員のモチベーションを高める (4時間)
セクハラやパワハラ、マタハラ防止の基礎知識から具体的事例まで、全社員の意識を高める実践型プログラムで安心な職場環境を実現します。
ハラスメント研修を効果的に実施するためのポイント
ハラスメント研修を効果的に実施するためのポイントは、以下の3点です。
- 具体的な事例が含まれている
- 研修内容が定期的にアップデートされている
- フォローアップがある
それぞれを見ていきましょう。
具体的な事例が含まれている
ハラスメント研修の内容に、具体的な事例が含まれていることがポイントです。
具体的な事例があることで、ハラスメントが発生する場面をイメージしやすくなります。現在の職場環境に置き換えられるため、受講者の理解が促進されます。
逆に具体例が無いと、知識を身につけても現場で活かしにくいです。研修内容には、具体的な事例を含め、イメージできるようにしましょう。
研修内容が定期的にアップデートされている
ハラスメント研修において、研修内容が定期的にアップデートされているのも大切です。
ハラスメントは、時代によって変化します。パワハラやセクハラなど、昔は問題なかった発言や行動も、現在では問題視されています。定期的にアップデートしないと、時代に合わないハラスメント研修になるため、効果が期待できません。
時代に合った研修ができるよう、内容はアップデートしておきましょう。
フォローアップがある
ハラスメント研修の実施後に、フォローアップがあることもポイントです。
フォローアップでは、ハラスメントが起きない環境作りを徹底するため、面談やアンケートなどのフォローアップを実施しましょう。現場の管理職と人事担当者で協力して、ハラスメント防止に努めることが大切です。
また、社員自身がハラスメントを受けてしまったときの対応方法を知っておくことも重要です。研修の最後には、社内や外部に相談窓口があることを伝え、相談先があることを覚えておいてもらいましょう。
ハラスメント研修についてよくある質問
ハラスメント研修についてよくある質問は、以下の4点です。
- 今までハラスメント事例はありませんが、研修は必要ですか?
- 対面の研修とオンライン研修ではどちらが効果的ですか?
- 優先的に受けるとよいハラスメント研修の種類はどれですか?
- ハラスメント研修の資料はもらえますか?
それぞれを見ていきましょう。
- Q. 今までハラスメント事例はありませんが、研修は必要ですか?
-
必要です。
ハラスメントが起こらないように防ぐことが、なにより重要だからです。今後もハラスメントと無縁の職場でいるためにも、研修を通して社員の意識と行動を振り返るきっかけ作りとして開催しましょう。
また、ハラスメントが無いのには理由があります。それを明確にすることで社員がそれぞれの行動や仕事に自信がもてます。
職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務です。
- Q. 対面の研修とオンライン研修ではどちらが効果的ですか?
-
どちらでも効果的です。
集合研修の場合は参加者が一堂に会するため、研修内容についての共通認識が作りやすい、他の人との考えの違いや共通点を見つけやすいなどのメリットがあります。
eラーニングは、時間的な縛りが少なく移動も無いことから仕事に支障をきたしにくい、シフト制の仕事でも対応しやすいなどのメリットがあります。また、集合研修では日程調整が大変、eラーニングでは参加者のモチベーションが下がるなどがデメリットです。
自社の働き方と、求める効果を考えて選びましょう。
- Q. 優先的に受けるとよいハラスメント研修の種類はどれですか?
-
パワハラとセクハラについてはビジネスの場面で起こりやすいため、優先すべき種類です。
また、親睦会等が多い場合はアルコールハラスメント、喫煙者が多い場合はスモークハラスメントなど、自社の特徴を捉えたものがよいです。
ハラスメント研修はハラスメントに対する知識を深め、起こさせない職場作りを目指すために実施します。個別の種類にこだわらず、ハラスメント全体を理解することから始めるのが大切です。
- Q. ハラスメント研修の資料はもらえますか?
-
研修によっては、資料がもらえます。
研修会社に資料がほしい旨を伝えることで、もらえるケースもあります。詳しくは、研修会社に問い合わせて確認しましょう。
ハラスメント研修を実施してハラスメントを抑止しよう
ハラスメント研修は、ハラスメントの防止や社員のリテラシー強化などが目的です。研修の効果を高めるためには、研修内容に具体的な事例を含めたり、定期的なアップデートを行いましょう。
自社内だけでのハラスメント研修実施が難しい場合は、専門の研修会社に依頼するのもおすすめです。
キーセッションでは、さまざまな研修会社のなかから、貴社のご要望に沿ったハラスメント研修をご提案します。相談は無料なので、関心がある方は気軽にお問い合わせください。


























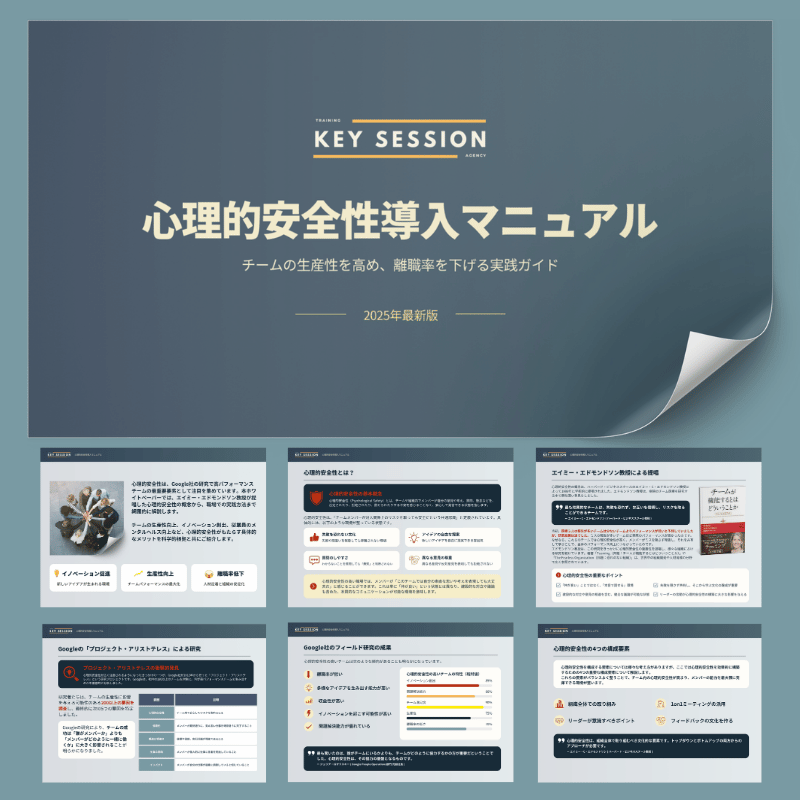


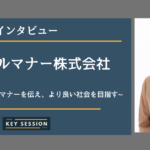

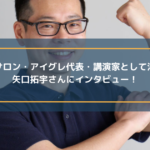

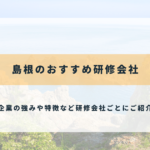
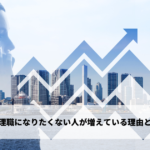

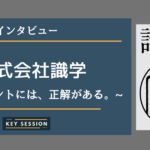

 研修の導入を徹底サポート
研修の導入を徹底サポート